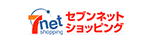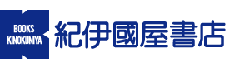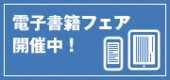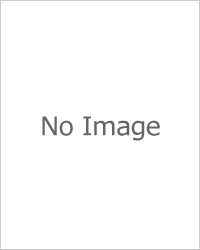
| 著者 | 武田 俊輔 著 |
|---|---|
| ジャンル | 環境・震災・都市・地域社会 |
| 出版年月日 | 2019/04/08 |
| ISBN | 9784788516298 |
| 判型・ページ数 | A5・332ページ |
| 定価 | 本体4,600円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
縮小する地方都市の伝統は現代においていかに継承されるのか。近世以来の祭礼を通じて負担と名誉を分ちあう「町内」社会の変容とダイナミズム,観光や文化財行政を通じて編成される都市のネットワークを,コモンズ論の視点から分析する気鋭の挑戦。
コモンズとしての都市祭礼 目次
第?部 課題の設定と分析視角
第1章 本書の目的と研究の視角
第1節 課題の設定
第2節 研究対象と分析の視角
第3節 本書の構成
第2章 都市社会学における「町内」社会研究の不在とその可能性
第1節 戦後日本の都市社会学における「町内」
第2節 都市社会学における「家」と「町内」社会
第3節 都市民俗学と都市人類学における都市研究
第3章 本書の分析視角コモンズとしての都市祭礼
第1節 地域資源の利用と管理を通じた生活共同
第2節 コモンズ論からの都市祭礼へのアプローチ
第3節 分析視角都市祭礼の構成資源の調達と用益の創出・配分をめぐる社会関係
第?部 都市祭礼を構成する諸資源・用益と祭礼の伝承メカニズム
第4章 山組における家と世代祭礼をめぐるコンフリクトとダイナミズム
第1節 山組内での祭礼の管理におけるコンフリクトの意味
第2節 祭礼における若衆たちの負担と祭礼の準備A町を事例として
第3節 祭礼における家・世代間の負担と名誉の配分
第4節 積極的に楽しまれ創出されるコンフリクト
第5節 マニュアルなき祭礼の管理と伝統のダイナミズム
第5章 山組間における対抗関係の管理と興趣の生産・配分裸参りを手がかりとして
第1節 複数の町内間における対抗関係の管理
第2節 裸参りの持つ意味とその手順
第3節 裸参りにおけるルールと喧嘩のプロセス
第4節 見物人の存在と対抗関係への作用
第5節 対抗関係の管理における暗黙の了解と協力
第6章 シャギリをめぐる山組間の協力と山組組織の再編
第1節 シャギリの調達を通した山組組織の再編
第2節 雇いシャギリの確保の困難と囃子保存会結成への動き
第3節 山組内でのシャギリ方の育成と山組の継承システムへの影響
第4節 シャギリを通じた祭礼の開放と人的資源の調達の変容
第7章 若衆たちの資金調達と社会的ネットワークの活用
第1節 祭礼における町内・町内間を越えた社会的ネットワークの活用
第2節 祭礼をめぐる資金の調達と若衆のネットワーク
第3節 協賛金獲得へのとりくみと用いられるネットワーク
第4節 協賛金集めの不合理性が持つ意味
第5節 社会関係資本の表象としての資金と相互給付関係、社会的ネットワーク
第8章 曳山をめぐる共同性と公共性共有資産としての曳山の管理とその変容
第1節 曳山の管理と公共的な用益の提供
第2節 1980年代以前の曳山の管理をめぐる社会関係
第3節 中心市街地の衰退と曳山博物館構想の曲折
第4節 文化財という文脈の活用と曳山の管理をめぐる矛盾
第5節 公(共)的な意味づけを活用した共同的な管理
第?部 コモンズとしての都市祭礼/地域社会/公共性
第9章 観光・市民の祭り・文化財公共的用益の活用と祭礼の意味づけの再編成
第1節 祭礼の公共的用益への提供とその再編成
第2節 戦前期大衆観光の流行と祭典補助費1924年~1937年
第3節 観光資源という文脈の活用と市財政への依存1950年~1965年
第4節 協賛会の設立と財団法人化の挫折1966年~1978年
第5節 文化財指定と複数の公共的文脈の併存1979年以後
第6節 公共的な用益を通じた諸資源の獲得と地域社会における関係性の広がり
第10章 本書における知見の整理と結論
第1節 都市祭礼を通してみる社会関係とネットワークの変容
第2節 コモンズとしての都市祭礼
第3節 都市社会学に対する本書の意義
第4節 本書の課題と展望
注
近現代長浜曳山祭年表
あとがき
参考文献
索引
装幀=加藤賢一
第?部 課題の設定と分析視角
第1章 本書の目的と研究の視角
第1節 課題の設定
第2節 研究対象と分析の視角
第3節 本書の構成
第2章 都市社会学における「町内」社会研究の不在とその可能性
第1節 戦後日本の都市社会学における「町内」
第2節 都市社会学における「家」と「町内」社会
第3節 都市民俗学と都市人類学における都市研究
第3章 本書の分析視角コモンズとしての都市祭礼
第1節 地域資源の利用と管理を通じた生活共同
第2節 コモンズ論からの都市祭礼へのアプローチ
第3節 分析視角都市祭礼の構成資源の調達と用益の創出・配分をめぐる社会関係
第?部 都市祭礼を構成する諸資源・用益と祭礼の伝承メカニズム
第4章 山組における家と世代祭礼をめぐるコンフリクトとダイナミズム
第1節 山組内での祭礼の管理におけるコンフリクトの意味
第2節 祭礼における若衆たちの負担と祭礼の準備A町を事例として
第3節 祭礼における家・世代間の負担と名誉の配分
第4節 積極的に楽しまれ創出されるコンフリクト
第5節 マニュアルなき祭礼の管理と伝統のダイナミズム
第5章 山組間における対抗関係の管理と興趣の生産・配分裸参りを手がかりとして
第1節 複数の町内間における対抗関係の管理
第2節 裸参りの持つ意味とその手順
第3節 裸参りにおけるルールと喧嘩のプロセス
第4節 見物人の存在と対抗関係への作用
第5節 対抗関係の管理における暗黙の了解と協力
第6章 シャギリをめぐる山組間の協力と山組組織の再編
第1節 シャギリの調達を通した山組組織の再編
第2節 雇いシャギリの確保の困難と囃子保存会結成への動き
第3節 山組内でのシャギリ方の育成と山組の継承システムへの影響
第4節 シャギリを通じた祭礼の開放と人的資源の調達の変容
第7章 若衆たちの資金調達と社会的ネットワークの活用
第1節 祭礼における町内・町内間を越えた社会的ネットワークの活用
第2節 祭礼をめぐる資金の調達と若衆のネットワーク
第3節 協賛金獲得へのとりくみと用いられるネットワーク
第4節 協賛金集めの不合理性が持つ意味
第5節 社会関係資本の表象としての資金と相互給付関係、社会的ネットワーク
第8章 曳山をめぐる共同性と公共性共有資産としての曳山の管理とその変容
第1節 曳山の管理と公共的な用益の提供
第2節 1980年代以前の曳山の管理をめぐる社会関係
第3節 中心市街地の衰退と曳山博物館構想の曲折
第4節 文化財という文脈の活用と曳山の管理をめぐる矛盾
第5節 公(共)的な意味づけを活用した共同的な管理
第?部 コモンズとしての都市祭礼/地域社会/公共性
第9章 観光・市民の祭り・文化財公共的用益の活用と祭礼の意味づけの再編成
第1節 祭礼の公共的用益への提供とその再編成
第2節 戦前期大衆観光の流行と祭典補助費1924年~1937年
第3節 観光資源という文脈の活用と市財政への依存1950年~1965年
第4節 協賛会の設立と財団法人化の挫折1966年~1978年
第5節 文化財指定と複数の公共的文脈の併存1979年以後
第6節 公共的な用益を通じた諸資源の獲得と地域社会における関係性の広がり
第10章 本書における知見の整理と結論
第1節 都市祭礼を通してみる社会関係とネットワークの変容
第2節 コモンズとしての都市祭礼
第3節 都市社会学に対する本書の意義
第4節 本書の課題と展望
注
近現代長浜曳山祭年表
あとがき
参考文献
索引
装幀=加藤賢一