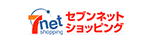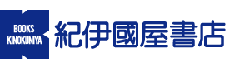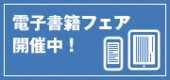インタラクションの認知科学
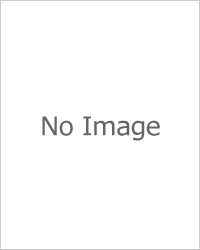
| 著者 | 日本認知科学会 監修 今井 倫太 著 内村 直之 ファシリテータ 植田 一博 アドバイザ |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 認知 |
| シリーズ | 「認知科学のススメ」シリーズ |
| 出版年月日 | 2018/06/22 |
| ISBN | 9784788515819 |
| 判型・ページ数 | 4-6・148ページ |
| 定価 | 本体1,600円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
ヒトを超えるAIが喧伝される一方,いまだロボットとの会話はぎこちない。注意を使うロボット/状況のわかるロボット/状況を共有するロボットなど,ヒトの認知特性に合わせたロボット開発から,社会の一員として暮らせるロボットの可能性を探る。
インタラクションの認知科学――目次
まえがき
1章 ロボットとの会話
ロボットの進出
身近になったロボット
ロボットを作るのに必要なこと
社会の中のロボット
いろいろなロボットとのコミュニケーション
命令で道具として働くロボット
遠隔地の人同士をつなぐロボット
人の相手ができるロボット
Column 続々登場しているコミュニケーション型ロボット
ロボットとの会話
情報を伝えるもの
会話と状況
状況で決まることばの意味
ロボットを用いた認知科学研究
Column 科学実験に使いにくい「人」
ロボットによるコミュニケーション実験とは……
実験の設計は難しい
行動記録やアンケートから結果を分析
インタラクションとは
違いは何?
Column ふつうの用語が難しい
人と機械のあいだは……
お互いの状態を知りたいがわからない!
わかりやすい機械か、人をわかる機械か
人とロボットのおつきあいは……
ロボット特有のやりかたもある
ロボットにお付き合いしてあげると
ロボットは世界をどう見たらいいのか
共有、その深淵な課題
関連性理論から見た影響と情報
言葉で伝えられないクオリア
情報の共有で信頼関係に
本書の構成
2章 注意と状況―ロボットに注意を使わせる
状況を理解するための注意機構
自明な状況は省略される
必須な「注意機構」という仕組み
注意を向けられるロボットを作る
注意機構を持つロボットとは
前方に障害があるとき
ロボットは知識表現を使う
「ダメ!」に反応するには
意図的注意・反射的注意を備えたロボット
注意の結果で変わる返答
より人に近いロボットLinta-II登場
なぜ発言が違うのか
注意機構と機能モジュールはやりとりする
注意機構を介してモジュール間の影響がある
注意機構がからむのが大事なわけ
Column フレーム問題
意図的注意と反射的注意をどう作る?
勝ち残った情報へ注意を向ける
競争による意図的注意の実現
競争による情報の決定
競争による意図的注意と反射的注意の両立
注意対象への興味は時間とともに減衰する
Linta-IIの注意機構はこう働く
自発的に注意を向けるロボット
3章 ことばの意味と状況と注意
状況意味論から考えると……
意味は状況の中で決まる
意味と世界
状況を取得できないとロボットはこまってしまう
談話状況と記述状況
2種類の「状況」がぶつかって
「同じ言葉」でも「違う意味」という場合
知らないことがあれば……
状況がわかるロボットを作るには
式にしないとロボットは理解不能
Linta-Iと状況理解
4章 共同注意と状況の共有
共同注意
同じ状況への注目が不可欠
お互いの心の窓を通す
共同注意とは心の状態を読み合うこと
指示語の意味がわかる
ロボットが創る共同注意
ロボットの思いはヒトに通じるか
視線を動かせば注意を誘導できる
人のアイコンタクトも引き起こす
ロボット側の共同注意は難しい
共同注意の先にあるもの
5章 関係性から心の理論へ
ロボットとつきあうために「関係性」が必要
見知らぬロボットと仲良くなる
「イタコシステム」で関係を付ける
ロボットとの関係性の有無で人の行動が違う実験
「おばけ」キャラが「憑依」する
人はロボットの言うことに耳を傾けるか
関係性が相手の言葉の理解に影響する
「人の心を読む」=心の理論の大切さ
人は無意識のうちに人の心を読んでいる
心を読めばいろいろなことができる
ロボットの「心」も読める?
6章 情報共有に基づくインタラクション
指差し示せば情報共有ができる
人の指差しの意味をロボットはわかるか
指差しながらロボットに指示する
人とロボットは情報共有できるか
同時性こそ「情報共有」のあかし
戦国時代の「情報共有戦」は……
一足先に顔を向けるロボットに人は一安心
事前に備わっている情報を利用した情報共有
会話で大事な五感についての話題
五感共有はロボットと人でも有効か
暖かい日、冷たいお茶、そしてチョコ
景色とおみやげに反応するか
ロボットの文脈に乗って楽しんだ人
心の理論のスイッチオン!
7章 ロボットの社会性と未来
達成できたこと,できなかったこと
社会性を与える/確認させる
社会の一員となるロボット
あとがき
文献一覧
索引
装 幀=荒川伸生
イラスト=大橋慶子
まえがき
1章 ロボットとの会話
ロボットの進出
身近になったロボット
ロボットを作るのに必要なこと
社会の中のロボット
いろいろなロボットとのコミュニケーション
命令で道具として働くロボット
遠隔地の人同士をつなぐロボット
人の相手ができるロボット
Column 続々登場しているコミュニケーション型ロボット
ロボットとの会話
情報を伝えるもの
会話と状況
状況で決まることばの意味
ロボットを用いた認知科学研究
Column 科学実験に使いにくい「人」
ロボットによるコミュニケーション実験とは……
実験の設計は難しい
行動記録やアンケートから結果を分析
インタラクションとは
違いは何?
Column ふつうの用語が難しい
人と機械のあいだは……
お互いの状態を知りたいがわからない!
わかりやすい機械か、人をわかる機械か
人とロボットのおつきあいは……
ロボット特有のやりかたもある
ロボットにお付き合いしてあげると
ロボットは世界をどう見たらいいのか
共有、その深淵な課題
関連性理論から見た影響と情報
言葉で伝えられないクオリア
情報の共有で信頼関係に
本書の構成
2章 注意と状況―ロボットに注意を使わせる
状況を理解するための注意機構
自明な状況は省略される
必須な「注意機構」という仕組み
注意を向けられるロボットを作る
注意機構を持つロボットとは
前方に障害があるとき
ロボットは知識表現を使う
「ダメ!」に反応するには
意図的注意・反射的注意を備えたロボット
注意の結果で変わる返答
より人に近いロボットLinta-II登場
なぜ発言が違うのか
注意機構と機能モジュールはやりとりする
注意機構を介してモジュール間の影響がある
注意機構がからむのが大事なわけ
Column フレーム問題
意図的注意と反射的注意をどう作る?
勝ち残った情報へ注意を向ける
競争による意図的注意の実現
競争による情報の決定
競争による意図的注意と反射的注意の両立
注意対象への興味は時間とともに減衰する
Linta-IIの注意機構はこう働く
自発的に注意を向けるロボット
3章 ことばの意味と状況と注意
状況意味論から考えると……
意味は状況の中で決まる
意味と世界
状況を取得できないとロボットはこまってしまう
談話状況と記述状況
2種類の「状況」がぶつかって
「同じ言葉」でも「違う意味」という場合
知らないことがあれば……
状況がわかるロボットを作るには
式にしないとロボットは理解不能
Linta-Iと状況理解
4章 共同注意と状況の共有
共同注意
同じ状況への注目が不可欠
お互いの心の窓を通す
共同注意とは心の状態を読み合うこと
指示語の意味がわかる
ロボットが創る共同注意
ロボットの思いはヒトに通じるか
視線を動かせば注意を誘導できる
人のアイコンタクトも引き起こす
ロボット側の共同注意は難しい
共同注意の先にあるもの
5章 関係性から心の理論へ
ロボットとつきあうために「関係性」が必要
見知らぬロボットと仲良くなる
「イタコシステム」で関係を付ける
ロボットとの関係性の有無で人の行動が違う実験
「おばけ」キャラが「憑依」する
人はロボットの言うことに耳を傾けるか
関係性が相手の言葉の理解に影響する
「人の心を読む」=心の理論の大切さ
人は無意識のうちに人の心を読んでいる
心を読めばいろいろなことができる
ロボットの「心」も読める?
6章 情報共有に基づくインタラクション
指差し示せば情報共有ができる
人の指差しの意味をロボットはわかるか
指差しながらロボットに指示する
人とロボットは情報共有できるか
同時性こそ「情報共有」のあかし
戦国時代の「情報共有戦」は……
一足先に顔を向けるロボットに人は一安心
事前に備わっている情報を利用した情報共有
会話で大事な五感についての話題
五感共有はロボットと人でも有効か
暖かい日、冷たいお茶、そしてチョコ
景色とおみやげに反応するか
ロボットの文脈に乗って楽しんだ人
心の理論のスイッチオン!
7章 ロボットの社会性と未来
達成できたこと,できなかったこと
社会性を与える/確認させる
社会の一員となるロボット
あとがき
文献一覧
索引
装 幀=荒川伸生
イラスト=大橋慶子