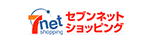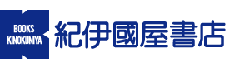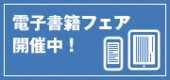東大闘争の語り
社会運動の予示と戦略
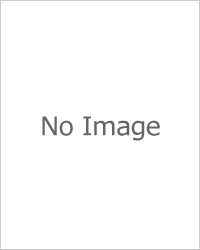
| 著者 | 小杉 亮子 著 |
|---|---|
| ジャンル | 社会学 > 歴史社会学 |
| 出版年月日 | 2018/05/15 |
| ISBN | 9784788515741 |
| 判型・ページ数 | A5・480ページ |
| 定価 | 本体3,900円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
深い分断と対立を経て東大闘争は何を遺したのか。党派や立場の異なる語り手44人が半世紀後に明かす闘争の全局面。語り手の生活史を掘り起こし,1960年代学生運動の予示的政治の力を描き切る。社会運動史の新しい扉をひらき称賛と共感を呼ぶ。
東大闘争の語り――目次
第?部 本書の課題と方法論
第1章 日本の?1968?とはなんだったのか――本書の課題
1 国境を越えた若者運動とその遺産
2 日本の社会運動における世代間の断絶
3 先行研究の限界――一九六〇年代学生運動の内在的理解に向けて
4 本書の観点――予示と戦略の対立
5 本書の構成
第2章 社会運動論の文化的アプローチと生活史分析――本書の方法論
1 社会運動論の文化的アプローチ
2 生活史をもちいた社会運動の分析
3 事例としての東大闘争の位置づけ
4 聞き取り調査の概要
第?部 東大闘争の形成と展開の過程
第3章 一九六〇年代学生運動のアクターたち――人間的基礎をたどる
1 政治的社会化の分析視角
2 ?自分より貧しい人びとがいる?という悲憤――社会集団への帰属意識
3 民青活動家の父・祖父たち――政治的社会化の場としての家庭・家族
4 戦後教育の変動と一九六〇年代学生運動のアクターたち――政治的社会化の場としての学校・教育
5 逆コースに対抗する教師たち
6 戦争にたいする感受性の形成
第4章 一九五〇―六〇年代の学生運動文化とその変容
1 運動文化の分析視角――キャンパスの学生運動文化をとらえる
2 東大キャンパスにおける学生運動文化の特徴
3 学生運動文化の変容と多元化
4 党派選択の論理
第5章 東大闘争の発生過程――参入するアクターと主体化するアクター
1 闘争の開始点――一九六七―六八年五月
2 闘争の全学化――一九六八年六月
3 自生的組織の簇生――一九六八年七月―一〇月
4 文学部8日間団交に見るノンセクト・新左翼・民青の違い――一九六八年一一月(1)
第6章 東大闘争の展開過程――アクターの分極化
1 学生間対立の深刻化――一九六八年一一月(2)
2 混迷のなかの分極化――一九六八年一二月―六九年一月
3 7学部集会と安田講堂攻防戦――一九六九年一月
第7章 東大闘争の収束過程――アクターの連続と断絶
1 高揚期の収束へ――一九六九年二月―一二月
2 主体化と方針の転換――一九六九―七〇年代前半(1)
3 移行と離脱――一九六九―七〇年代前半(2)
第?部 一九六〇年代学生運動の位相 337
第8章 グローバル・シックスティーズのなかの日本
1 グローバルな現象としての?1968?
2 グローバル・シックスティーズ論から見る日本の?1968?
第9章 社会運動の予示と戦略――戦後社会運動史のなかの一九六〇年代学生運動
1 新しい学生運動の表現としての全共闘
2 東大闘争参加者たちのその後
3 一九六〇年代学生運動の歴史的位置
終 章 多元的アクターの相克と主体化
1 東大闘争の遺産
2 否定的な集合的記憶を越えて
あとがき
参考文献・図表一覧
事項索引・人名索引
装幀 鈴木敬子(pagnigh-magnigh)
第?部 本書の課題と方法論
第1章 日本の?1968?とはなんだったのか――本書の課題
1 国境を越えた若者運動とその遺産
2 日本の社会運動における世代間の断絶
3 先行研究の限界――一九六〇年代学生運動の内在的理解に向けて
4 本書の観点――予示と戦略の対立
5 本書の構成
第2章 社会運動論の文化的アプローチと生活史分析――本書の方法論
1 社会運動論の文化的アプローチ
2 生活史をもちいた社会運動の分析
3 事例としての東大闘争の位置づけ
4 聞き取り調査の概要
第?部 東大闘争の形成と展開の過程
第3章 一九六〇年代学生運動のアクターたち――人間的基礎をたどる
1 政治的社会化の分析視角
2 ?自分より貧しい人びとがいる?という悲憤――社会集団への帰属意識
3 民青活動家の父・祖父たち――政治的社会化の場としての家庭・家族
4 戦後教育の変動と一九六〇年代学生運動のアクターたち――政治的社会化の場としての学校・教育
5 逆コースに対抗する教師たち
6 戦争にたいする感受性の形成
第4章 一九五〇―六〇年代の学生運動文化とその変容
1 運動文化の分析視角――キャンパスの学生運動文化をとらえる
2 東大キャンパスにおける学生運動文化の特徴
3 学生運動文化の変容と多元化
4 党派選択の論理
第5章 東大闘争の発生過程――参入するアクターと主体化するアクター
1 闘争の開始点――一九六七―六八年五月
2 闘争の全学化――一九六八年六月
3 自生的組織の簇生――一九六八年七月―一〇月
4 文学部8日間団交に見るノンセクト・新左翼・民青の違い――一九六八年一一月(1)
第6章 東大闘争の展開過程――アクターの分極化
1 学生間対立の深刻化――一九六八年一一月(2)
2 混迷のなかの分極化――一九六八年一二月―六九年一月
3 7学部集会と安田講堂攻防戦――一九六九年一月
第7章 東大闘争の収束過程――アクターの連続と断絶
1 高揚期の収束へ――一九六九年二月―一二月
2 主体化と方針の転換――一九六九―七〇年代前半(1)
3 移行と離脱――一九六九―七〇年代前半(2)
第?部 一九六〇年代学生運動の位相 337
第8章 グローバル・シックスティーズのなかの日本
1 グローバルな現象としての?1968?
2 グローバル・シックスティーズ論から見る日本の?1968?
第9章 社会運動の予示と戦略――戦後社会運動史のなかの一九六〇年代学生運動
1 新しい学生運動の表現としての全共闘
2 東大闘争参加者たちのその後
3 一九六〇年代学生運動の歴史的位置
終 章 多元的アクターの相克と主体化
1 東大闘争の遺産
2 否定的な集合的記憶を越えて
あとがき
参考文献・図表一覧
事項索引・人名索引
装幀 鈴木敬子(pagnigh-magnigh)