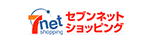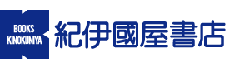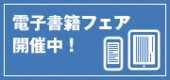日本の心理療法 国際比較篇
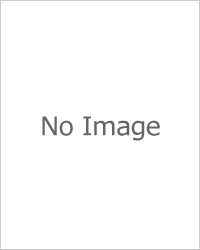
| 著者 | 秋田 巌 編 名取 琢自 編 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 臨床 |
| シリーズ | 日本の心理療法 |
| 出版年月日 | 2017/09/07 |
| ISBN | 9784788515307 |
| 判型・ページ数 | A5・224ページ |
| 定価 | 本体2,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
東洋的な価値観との精神的な融合を探求し続けたユング,欧州に長年在住した日本人の心理療法家,来日し仏門に入ったアメリカ人の心理療法家など,さまざまな心理臨床的異文化体験の比較を通じ,日本の心理療法場面における「局所性」を明らかにする。
日本の心理療法 国際比較篇――目次
はじめに(各篇共通)
序
国際比較篇――風土・物語・局所性
第一章 分析心理学における東洋と西洋の出会い
――国際的な視点から ポール・クーグラー
●分析心理学初期の歴史 ●ブルクヘルツリ精神科クリニック ●ピエール・ジャネと心理分析
●実験精神病理学研究所 ●ジークムント・フロイトと国際精神分析学会 ●ユングの自己実験――赤の書
●アクティブ・イマジネーション――ポスト植民地時代的臨床解釈学 ●自己――心の宇宙の中心
●東洋思想との対話を開く ●エラノス――国際的視点
第二章 心理療法における「美的なもの」について 樋口和彦
はじめに
本論文の基本的な論点について
基本的に「東」とは何を意味するか?
箱庭療法(Sandspiel Therapie)のわが国への導入について
なぜ河合隼雄は箱庭療法と訳したか?
心理療法における美的基準について
エラノス会議のテーマについて再考する
絶対性・絶対的人格神の理解の重要性について
イメージの遊び
第三章 日英「暮らしの文化」比較――心理臨床家の一考察 佐山菫子
「ふるさと」の発見
文化とは何か
ロンドンでの暮らし
英国とは何か
英国の成り立ち
日本とは何か
ロンドンに暮らす日本人
おわりに
第四章 歎異抄、昔話、近代文学、そして分析 ウルスラ・ヴァイス
はじめに
導入について
●浄土真宗における教えの継承 ●分析心理学における教えの継承 ●導入段階の「長い眠り」
「門」が意味するもの
●移行と変容 ●自我からの解脱 ●門に入る葛藤 ●門を抜ける困難 ●門を見つけること
おわりに――漱石の『門』
第五章 日本体験の再発見
――海外の心理臨床家との出会いを通して 名取琢自
「信じる」ことの三つの層
西洋の心理療法家の印象
●「大人」―「子ども」バランスの安定性と融通性(やわらかく、厳しく生きている)
●率直さ・直接性(さほど裏を読まなくてよい) ●信念――芯の感触(「私」をもっている)
●理性(言語)への信頼(議論できる) ●「存在するもの」への視線(見えるものへのまなざし)
●東洋的なものや異文化の尊重
日本の心理療法での人間関係とコミュニケーション
●「大人」―「子ども」の振れ幅と堅さ ●婉曲・間接性(裏を察すること)
●「信念」への不信(「私」を通すことの不安) ●感情の影響(根に持ちやすさ)
●「見えないもの」への視線(イメージの奥へのまなざし) ●東洋的なものの当然視(「甘え」)
おわりに――シェリー・シェパード氏の論考を参照して
第六章 国際的に見た日本の心理療法
――二〇一一・九・二三会議によせて シェリー・蓮夢・シェパード
「縁」の感覚
繊細さ
守秘の「器」
スピリチュアル・タイプ
第七章 西洋のサイコセラピーと東洋の心性
――認知行動療法の歴史的変遷を通して考える 遊佐安一郎
はじめに――日本での心理療法
欧米のサイコセラピーの傾向
認知行動療法――その三つの波
●第一の波――行動療法 ●第二の波――認知療法・認知行動療法 ●第三の波――従来の認知行動療法を超える新しい波
西洋のサイコセラピーと日本の心理療法
第八章 日本的風土と精神科医療の出会い 吉村夕里
はじめに
風土との出会い
●政策転換と法整備の時代 ●運動体の葛藤と精神科リハビリテーションの隆盛 ●愛憎の風土
精神科医療をめぐる時代の地理や政治や文化
●格差の存在 ●共同体に生きる人々 ●医療中断者たちへのアプローチ ●共同体の新参者と共同体から出立する人たち
日本的風土に精神科医療が与えたもの
おわりに
おわりに
事項索引
人名索引
装幀=虎尾 隆
はじめに(各篇共通)
序
国際比較篇――風土・物語・局所性
第一章 分析心理学における東洋と西洋の出会い
――国際的な視点から ポール・クーグラー
●分析心理学初期の歴史 ●ブルクヘルツリ精神科クリニック ●ピエール・ジャネと心理分析
●実験精神病理学研究所 ●ジークムント・フロイトと国際精神分析学会 ●ユングの自己実験――赤の書
●アクティブ・イマジネーション――ポスト植民地時代的臨床解釈学 ●自己――心の宇宙の中心
●東洋思想との対話を開く ●エラノス――国際的視点
第二章 心理療法における「美的なもの」について 樋口和彦
はじめに
本論文の基本的な論点について
基本的に「東」とは何を意味するか?
箱庭療法(Sandspiel Therapie)のわが国への導入について
なぜ河合隼雄は箱庭療法と訳したか?
心理療法における美的基準について
エラノス会議のテーマについて再考する
絶対性・絶対的人格神の理解の重要性について
イメージの遊び
第三章 日英「暮らしの文化」比較――心理臨床家の一考察 佐山菫子
「ふるさと」の発見
文化とは何か
ロンドンでの暮らし
英国とは何か
英国の成り立ち
日本とは何か
ロンドンに暮らす日本人
おわりに
第四章 歎異抄、昔話、近代文学、そして分析 ウルスラ・ヴァイス
はじめに
導入について
●浄土真宗における教えの継承 ●分析心理学における教えの継承 ●導入段階の「長い眠り」
「門」が意味するもの
●移行と変容 ●自我からの解脱 ●門に入る葛藤 ●門を抜ける困難 ●門を見つけること
おわりに――漱石の『門』
第五章 日本体験の再発見
――海外の心理臨床家との出会いを通して 名取琢自
「信じる」ことの三つの層
西洋の心理療法家の印象
●「大人」―「子ども」バランスの安定性と融通性(やわらかく、厳しく生きている)
●率直さ・直接性(さほど裏を読まなくてよい) ●信念――芯の感触(「私」をもっている)
●理性(言語)への信頼(議論できる) ●「存在するもの」への視線(見えるものへのまなざし)
●東洋的なものや異文化の尊重
日本の心理療法での人間関係とコミュニケーション
●「大人」―「子ども」の振れ幅と堅さ ●婉曲・間接性(裏を察すること)
●「信念」への不信(「私」を通すことの不安) ●感情の影響(根に持ちやすさ)
●「見えないもの」への視線(イメージの奥へのまなざし) ●東洋的なものの当然視(「甘え」)
おわりに――シェリー・シェパード氏の論考を参照して
第六章 国際的に見た日本の心理療法
――二〇一一・九・二三会議によせて シェリー・蓮夢・シェパード
「縁」の感覚
繊細さ
守秘の「器」
スピリチュアル・タイプ
第七章 西洋のサイコセラピーと東洋の心性
――認知行動療法の歴史的変遷を通して考える 遊佐安一郎
はじめに――日本での心理療法
欧米のサイコセラピーの傾向
認知行動療法――その三つの波
●第一の波――行動療法 ●第二の波――認知療法・認知行動療法 ●第三の波――従来の認知行動療法を超える新しい波
西洋のサイコセラピーと日本の心理療法
第八章 日本的風土と精神科医療の出会い 吉村夕里
はじめに
風土との出会い
●政策転換と法整備の時代 ●運動体の葛藤と精神科リハビリテーションの隆盛 ●愛憎の風土
精神科医療をめぐる時代の地理や政治や文化
●格差の存在 ●共同体に生きる人々 ●医療中断者たちへのアプローチ ●共同体の新参者と共同体から出立する人たち
日本的風土に精神科医療が与えたもの
おわりに
おわりに
事項索引
人名索引
装幀=虎尾 隆