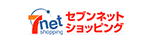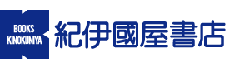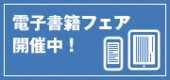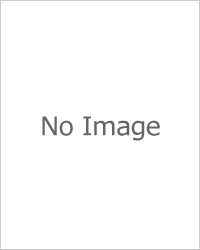
| 著者 | 矢守 克也 編 宮本 匠 編 |
|---|---|
| ジャンル | 環境・震災・都市・地域社会 |
| 出版年月日 | 2016/03/07 |
| ISBN | 9784788514669 |
| 判型・ページ数 | 4-6・208ページ |
| 定価 | 本体1,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
高さ30メートル超の大津波からどう逃れるか。原発災害による風評被害をどのように乗り越えるか。大災害を経た後も生き生きと充実した生を実現するには? 地域特性や直面する課題の異なるさまざまなフィールドで,「減災」のあり方を明らかにする。
現場(フィールド)でつくる減災学――目次
1章 減災学をつくる 矢守克也
1 五つのフロンティアを概観する
1-1 はじめに
1-2 減災社会プロジェクト
1-3 個別避難訓練タイムトライアル(2章)
1-4 サイエンスする市民(3章)
1-5 地域気象情報というコミュニケーション(4章)
1-6 被災地の住民がつくる防災教材(5章)
1-7 ことばによる減災アクション(6章)
1-8 減災学がめざすもの(7章)
2 「減災」について再考する─そのための三つの視点
2-1 プラスチックワード
2-2 第一の視点─コミュニケーション
2-3 第二の視点─ツール
2-4 第三の視点─コンセプト
2-5 何のための減災か
2章 個別避難訓練タイムトライアル 孫 英英
1 訓練当事者の主体性を取り戻すには
2 研究フィールドの概要
3 個別避難訓練と動画カルテ
3-1 個別避難訓練の実施の流れ
3-2 動画カルテの作成
4 個別避難訓練における「主体性」の回復
4-1 Aさんの事例
4-2 Bさんの事例
4-3 Cさんの事例
5 まとめ
3章 サイエンスする市民 矢守克也・岩堀卓弥
1 はじめに
2 阿武山観測所サイエンス・ミュージアム化構想
2-1 始動(2011年度)─観測施設からアウトリーチの拠点へ
2-2 転機(2012年度)─《阿武山サポーター》の誕生
2-3 発展(2013年度以降)─《サポーター》が自ら、そして外へ
3 満点計画学習プログラム
3-1 「満点計画」とは?
3-2 小学生が担う地震観測
3-3 満点計画学習プログラム
3-4 「担う」ことがもたらすこと
3-5 試行錯誤と今後の展望
4章 地域気象情報というコミュニケーション 竹之内健介
1 はじめに
1-1 あなたにとって気象情報はどんなもの?
1-2 地域の歴史と減災とのかかわりについて
2 地域気象情報とは
2-1 リスク・コミュニケーションの観点からみた気象情報
2-2 地域気象情報に含まれる三つの視点
3 伊勢市中島学区での取り組み
3-1 伊勢市中島学区の地理的特徴
3-2 取り組み・─生活防災
3-3 取り組み・─防災イベント
3-4 取り組み・─地域気象情報
3-5 伊勢市中島学区における現在の取り組み
4 地域気象情報がめざす社会のすがた
5章 被災地の住民がつくる防災教材 李{画像ファイル}risan.jpg_(フシン)
1 はじめに
1-1 複合災害時における判断の難しさ
1-2 「住民主体」とは何か
2 「クロスロード:大洗編」を導入するまで
2-1 茨城県大洗町の地理的特徴と被災状況
2-2 大洗町の復興に向けた地域の取り組み
3 「クロスロード:大洗編」の取り組み
3-1 「クロスロード」とは何か
3-2 「大洗編」の実践
3-3 「大洗編」の効果と反響
4 「クロスロード:大洗編」の意義
4-1 明確化・可視化
4-2 共通化・共有化
4-3 主体化
5 今後に向けて
6章 ことばによる減災アクション 近藤誠司
1 はじめに
2 ことばの創造力
3 「ぼうさい夢トーク」におけることば
3-1 等身大のことば
3-2 科学者である前に人である
3-3 過去の交絡─人としての歩み
3-4 未来の交絡─夢見ることばたち
3-5 当該実践の創造的なポテンシャル
4 「KOBE虹会」におけることば
4-1 溶け合うことば
4-2 現在の交絡─あるいは、他者との交歓
4-3 当該実践の創造的なポテンシャル
5 ことばの世界を超えて
7章 減災学がめざすもの 宮本 匠
1 防災と減災
2 孤独死が問いかけたもの
3 減災の主体
4 減災と復興
5 「Xがない」問題
6 減災の主体形成
7 「めざすかかわり」と「すごすかかわり」
8 本書の結びに
あとがき
文 献
■装幀=桂川 潤
1章 減災学をつくる 矢守克也
1 五つのフロンティアを概観する
1-1 はじめに
1-2 減災社会プロジェクト
1-3 個別避難訓練タイムトライアル(2章)
1-4 サイエンスする市民(3章)
1-5 地域気象情報というコミュニケーション(4章)
1-6 被災地の住民がつくる防災教材(5章)
1-7 ことばによる減災アクション(6章)
1-8 減災学がめざすもの(7章)
2 「減災」について再考する─そのための三つの視点
2-1 プラスチックワード
2-2 第一の視点─コミュニケーション
2-3 第二の視点─ツール
2-4 第三の視点─コンセプト
2-5 何のための減災か
2章 個別避難訓練タイムトライアル 孫 英英
1 訓練当事者の主体性を取り戻すには
2 研究フィールドの概要
3 個別避難訓練と動画カルテ
3-1 個別避難訓練の実施の流れ
3-2 動画カルテの作成
4 個別避難訓練における「主体性」の回復
4-1 Aさんの事例
4-2 Bさんの事例
4-3 Cさんの事例
5 まとめ
3章 サイエンスする市民 矢守克也・岩堀卓弥
1 はじめに
2 阿武山観測所サイエンス・ミュージアム化構想
2-1 始動(2011年度)─観測施設からアウトリーチの拠点へ
2-2 転機(2012年度)─《阿武山サポーター》の誕生
2-3 発展(2013年度以降)─《サポーター》が自ら、そして外へ
3 満点計画学習プログラム
3-1 「満点計画」とは?
3-2 小学生が担う地震観測
3-3 満点計画学習プログラム
3-4 「担う」ことがもたらすこと
3-5 試行錯誤と今後の展望
4章 地域気象情報というコミュニケーション 竹之内健介
1 はじめに
1-1 あなたにとって気象情報はどんなもの?
1-2 地域の歴史と減災とのかかわりについて
2 地域気象情報とは
2-1 リスク・コミュニケーションの観点からみた気象情報
2-2 地域気象情報に含まれる三つの視点
3 伊勢市中島学区での取り組み
3-1 伊勢市中島学区の地理的特徴
3-2 取り組み・─生活防災
3-3 取り組み・─防災イベント
3-4 取り組み・─地域気象情報
3-5 伊勢市中島学区における現在の取り組み
4 地域気象情報がめざす社会のすがた
5章 被災地の住民がつくる防災教材 李{画像ファイル}risan.jpg_(フシン)
1 はじめに
1-1 複合災害時における判断の難しさ
1-2 「住民主体」とは何か
2 「クロスロード:大洗編」を導入するまで
2-1 茨城県大洗町の地理的特徴と被災状況
2-2 大洗町の復興に向けた地域の取り組み
3 「クロスロード:大洗編」の取り組み
3-1 「クロスロード」とは何か
3-2 「大洗編」の実践
3-3 「大洗編」の効果と反響
4 「クロスロード:大洗編」の意義
4-1 明確化・可視化
4-2 共通化・共有化
4-3 主体化
5 今後に向けて
6章 ことばによる減災アクション 近藤誠司
1 はじめに
2 ことばの創造力
3 「ぼうさい夢トーク」におけることば
3-1 等身大のことば
3-2 科学者である前に人である
3-3 過去の交絡─人としての歩み
3-4 未来の交絡─夢見ることばたち
3-5 当該実践の創造的なポテンシャル
4 「KOBE虹会」におけることば
4-1 溶け合うことば
4-2 現在の交絡─あるいは、他者との交歓
4-3 当該実践の創造的なポテンシャル
5 ことばの世界を超えて
7章 減災学がめざすもの 宮本 匠
1 防災と減災
2 孤独死が問いかけたもの
3 減災の主体
4 減災と復興
5 「Xがない」問題
6 減災の主体形成
7 「めざすかかわり」と「すごすかかわり」
8 本書の結びに
あとがき
文 献
■装幀=桂川 潤