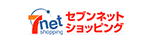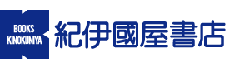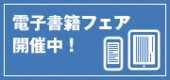少子化時代の「良妻賢母」
変容する現代日本の女性と家族
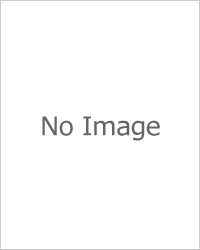
| 著者 | S. D. ハロウェイ 著 高橋 登 訳 清水 民子 訳 瓜生 淑子 訳 |
|---|---|
| ジャンル | 社会学 > 家族・女性・ジェンダー |
| 出版年月日 | 2014/07/24 |
| ISBN | 9784788513945 |
| 判型・ページ数 | 4-6・400ページ |
| 定価 | 本体3,700円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
なぜ日本の女性は結婚・子育てに前向きになれないのか? 政府の家族政策を歴史的に概観しつつ,現代の母親たちの考え方・行動パターンを詳細なインタビューを通して分析。「良妻賢母」イメージ,子育て観の変遷を女性の視点から浮き彫りにする。
少子化時代の「良妻賢母」――目次
緒 言
第一部
1章「良妻賢母」― 文化的な文脈のもとでの子育てと家庭生活
日本の母親は主観的には何を経験しているのか?
良妻賢母とは何か?
2章 研究の時間的・空間的な位置づけ
女性の声を聴く
本研究の行われた地域の状況
大阪の家族の現状
第二部
3章「賢母」とは
19世紀日本の家族と子育て
近代の子育ての営みの変化
「良母」はわが子を遠くから見守る
「良母」は子どもとのかかわり方を知っている
「良母」は感情的にならずに子どもを導く
母親がかかわれるのはどこまでか
結 論
4章 反省 ― 自己省察のプロセス
反省がもつ複数の意味
不安からのあがきか冷静な省察か
母親として自信のある分野とない分野
よいコミュニケーションを確立し肯定的な感情で結びつくことの難しさ
感情をコントロールし続けることの難しさ
子どもの学業をサポートすることの難しさ
学業のサポートに対する母親の自己評価に起きる変化
結 論
第三部
5章 子ども時代の記憶
恐れられる父親と沈黙する父親
温かい、気遣いのある父親とともに育つ
母親との初期の関係 ―支持と保護
成人して幼児期と折り合いをつける
結 論
6章 夫たち ― 重要なパートナーか、周辺の他人か?
現代の父親の家庭内活動への関与
結婚生活への視点 ―怒りと幻滅
なぜ不幸せな結婚生活にとどまるのか?
満足できる結婚生活の要件
夫からのサポートと妻の子育て効力感
結 論
第四部
7章 しつけ ― 子育ての秘訣
しつけの歴史的な意味
よい子とは? 社会的感受性への変わらぬ関心
自立をうながしながら依存の欲求を受け入れること
母親はどのようなしつけの方法を用いているのか?
適切な行動の必要性を理解させること
誰が助けてくれるのか? 夫、親、姑、友人の役割
結 論
8章 子どもの学校教育への母親の関与
近代日本における学校教育
学校教育をサポートする母親の役割
学校教育への親の関与と社会階層
調査結果からわかる学校教育に対する親の願い
親の自信は子どもの学校教育への関与と関係があるか?
なぜ日本の母親は子どもに高い願望をもたないのか?
学業について否定的な経験をし、子育ての自己効力感が低い順子の場合
学業について肯定的な経験をもち、子育ての自己効力感も高い美由紀の場合
例外的なパターン ―浅子と千尋
結 論
9章 仕事と家庭生活のバランスをとる
戦前日本の女性労働者 ―家庭生活よりも生産性
戦後期における女性と職業 ―家事志向への移行
女性から見た働くことの利点
M字型曲線の人生
夢をあきらめる ―美由紀の学校と職場の物語
職と刺激を求めて ―千尋の場合
若いときの夢と両親からのさまざまなサポート
仕事上の人間関係を良好に維持することの難しさ
退職すべき時を「決意させる」家族と雇用者からの圧力
職場に戻って
仕事をもつ母親の方がよい母親か?
結 論
10章 女性と家庭生活 ― イデオロギー、経験、行為主性
子育ての文化モデル ―母親に求められる高い基準
社会からの支援と批判の役割
家族に影響する制度的要因 ― 学校と職場からの要求
母親支援を模索する実践家たちへの示唆
文化心理学への理論的示唆
自己効力感理論への示唆
日本の出生率低下に関する政策への示唆
訳者あとがき
付録B
付録A
引用文献
事項索引
人名索引
訳者あとがき
緒 言
第一部
1章「良妻賢母」― 文化的な文脈のもとでの子育てと家庭生活
日本の母親は主観的には何を経験しているのか?
良妻賢母とは何か?
2章 研究の時間的・空間的な位置づけ
女性の声を聴く
本研究の行われた地域の状況
大阪の家族の現状
第二部
3章「賢母」とは
19世紀日本の家族と子育て
近代の子育ての営みの変化
「良母」はわが子を遠くから見守る
「良母」は子どもとのかかわり方を知っている
「良母」は感情的にならずに子どもを導く
母親がかかわれるのはどこまでか
結 論
4章 反省 ― 自己省察のプロセス
反省がもつ複数の意味
不安からのあがきか冷静な省察か
母親として自信のある分野とない分野
よいコミュニケーションを確立し肯定的な感情で結びつくことの難しさ
感情をコントロールし続けることの難しさ
子どもの学業をサポートすることの難しさ
学業のサポートに対する母親の自己評価に起きる変化
結 論
第三部
5章 子ども時代の記憶
恐れられる父親と沈黙する父親
温かい、気遣いのある父親とともに育つ
母親との初期の関係 ―支持と保護
成人して幼児期と折り合いをつける
結 論
6章 夫たち ― 重要なパートナーか、周辺の他人か?
現代の父親の家庭内活動への関与
結婚生活への視点 ―怒りと幻滅
なぜ不幸せな結婚生活にとどまるのか?
満足できる結婚生活の要件
夫からのサポートと妻の子育て効力感
結 論
第四部
7章 しつけ ― 子育ての秘訣
しつけの歴史的な意味
よい子とは? 社会的感受性への変わらぬ関心
自立をうながしながら依存の欲求を受け入れること
母親はどのようなしつけの方法を用いているのか?
適切な行動の必要性を理解させること
誰が助けてくれるのか? 夫、親、姑、友人の役割
結 論
8章 子どもの学校教育への母親の関与
近代日本における学校教育
学校教育をサポートする母親の役割
学校教育への親の関与と社会階層
調査結果からわかる学校教育に対する親の願い
親の自信は子どもの学校教育への関与と関係があるか?
なぜ日本の母親は子どもに高い願望をもたないのか?
学業について否定的な経験をし、子育ての自己効力感が低い順子の場合
学業について肯定的な経験をもち、子育ての自己効力感も高い美由紀の場合
例外的なパターン ―浅子と千尋
結 論
9章 仕事と家庭生活のバランスをとる
戦前日本の女性労働者 ―家庭生活よりも生産性
戦後期における女性と職業 ―家事志向への移行
女性から見た働くことの利点
M字型曲線の人生
夢をあきらめる ―美由紀の学校と職場の物語
職と刺激を求めて ―千尋の場合
若いときの夢と両親からのさまざまなサポート
仕事上の人間関係を良好に維持することの難しさ
退職すべき時を「決意させる」家族と雇用者からの圧力
職場に戻って
仕事をもつ母親の方がよい母親か?
結 論
10章 女性と家庭生活 ― イデオロギー、経験、行為主性
子育ての文化モデル ―母親に求められる高い基準
社会からの支援と批判の役割
家族に影響する制度的要因 ― 学校と職場からの要求
母親支援を模索する実践家たちへの示唆
文化心理学への理論的示唆
自己効力感理論への示唆
日本の出生率低下に関する政策への示唆
訳者あとがき
付録B
付録A
引用文献
事項索引
人名索引
訳者あとがき