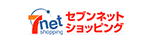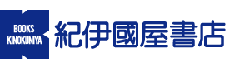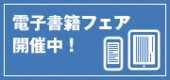〈高卒当然社会〉の戦後史
誰でも高校に通える社会は維持できるのか
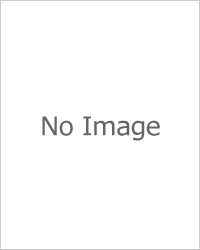
| 著者 | 香川 めい 著 児玉 英靖 著 相澤 真一 著 |
|---|---|
| ジャンル | 社会学 > 歴史社会学 |
| 出版年月日 | 2014/07/22 |
| ISBN | 9784788513952 |
| 判型・ページ数 | 4-6・240ページ |
| 定価 | 本体2,300円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
同世代の半数以下しか進学しなかった時代から,わずか20年で「高卒で当然」となった日本。この大改革はいかに実行され何をもたらしたのか。高校教育拡大の歴史を跡付け,少子化時代を迎えた「誰でも高校に通える社会」の未来を占う実証分析の労作。
〈高卒当然社会〉の戦後史――目次
はじめに 「高校に通えることが当たり前の社会」の成り立ち
―高校教育機会の提供構造とは
序 章 今、なぜ「誰でも通える社会」について考えるのか
〈高卒当然社会〉の成立
本書の学術研究上の意義について
第1章 新制高等学校黎明期から見る高校教育機会の提供構造
1 全国一律の「高校」という制度
2 高校教育提供構造の地域性
3 高校教育における教育機会の平等とは―学区制の議論から
第1章のまとめ
第2章 一九六〇年代の高校教育拡大は何をもたらしたのか
1 第一次ベビーブーマーの高校進学が与えたインパクト
2 高校進学率の上昇は、高卒学歴の持つ意味をどう変えたのか?
―高卒学歴に人々が期待していたものとその裏切り
3 「誰でも高校に通える社会」はなぜ可能となったのか?
―私立高校が引き起こした高校教育拡大のスパイラル
第2章のまとめと地域性への問いの展開
第3章 高校教育機会の提供構造の地域的布置と類型化
1 地域によって異なる私立高校依存度
2 都道府県の類型化
3 各類型の特徴と高校の威信構造における地域性
第3章のまとめ
第4章 各都道府県のケーススタディ(1)中庸型
―静岡県・香川県・兵庫県
はじめに―第4章から第7章のケーススタディについて
中庸型の三県(静岡県・香川県・兵庫県)の検討
1 静岡県―日本の社会経済システムの「縮図」における教育拡大
2 香川県―大規模化した公立高校とバッファーとしての私立高校で数年を乗り切る
3 兵庫県―大都市圏と広大な中山間地域の併存がもたらした県内の多様性
中庸型クラスターのケーススタディのまとめ
コラム 大学附属高校と高校教育拡大
第5章 各都道府県のケーススタディ(2)公立拡張型
―徳島県・愛知県
1 徳島県―山地の多い地域で「平均並み」を求める取り組みと私立高校への低い信頼感
2 愛知県―比率による高校教育機会の提供構造によって拡大した進学率
公立拡張型クラスターのケーススタディのまとめ
第6章 各都道府県のケーススタディ(3)私立拡張型
―宮崎県・山形県・群馬県
1 宮崎県―全国最低の進学率から「平均」への取り組み
2 山形県―新設された私立高校による公立高校不足の補完
3 群馬県―男女別学を前提とした高校教育機会の拡大
私立拡張型クラスターのケーススタディのまとめ
コラム 甲子園(一)
第7章 各都道府県のケーススタディ(4)大都市型
―大阪府・神奈川県
1 大阪府―マンモス私立高校による高校進学希望者の収容とその結末
2 神奈川県―急激な人口増に対応した公立高校の増設と二極化した私立高校の対応
ケーススタディによる四つのクラスターの検討のまとめ
コラム 東京(一)
コラム 東京(二)
第8章 拡大した高校教育のその後
―生徒減少期における高校教育機会の近未来像
はじめに―生徒減少期における高校教育機会提供構造の変容
1 生徒減少期における私学率の規定要因の変化
2 特徴的な県の検討?―神奈川県の事例から
3 特徴的な県の検討?―徳島県の事例から
第8章のまとめ
コラム 甲子園(二)
終 章 人口減少期における〈高卒当然社会〉のゆくえ
高校教育機会の提供構造の将来像
あとがき
初出一覧
索 引
装幀=難波園子
はじめに 「高校に通えることが当たり前の社会」の成り立ち
―高校教育機会の提供構造とは
序 章 今、なぜ「誰でも通える社会」について考えるのか
〈高卒当然社会〉の成立
本書の学術研究上の意義について
第1章 新制高等学校黎明期から見る高校教育機会の提供構造
1 全国一律の「高校」という制度
2 高校教育提供構造の地域性
3 高校教育における教育機会の平等とは―学区制の議論から
第1章のまとめ
第2章 一九六〇年代の高校教育拡大は何をもたらしたのか
1 第一次ベビーブーマーの高校進学が与えたインパクト
2 高校進学率の上昇は、高卒学歴の持つ意味をどう変えたのか?
―高卒学歴に人々が期待していたものとその裏切り
3 「誰でも高校に通える社会」はなぜ可能となったのか?
―私立高校が引き起こした高校教育拡大のスパイラル
第2章のまとめと地域性への問いの展開
第3章 高校教育機会の提供構造の地域的布置と類型化
1 地域によって異なる私立高校依存度
2 都道府県の類型化
3 各類型の特徴と高校の威信構造における地域性
第3章のまとめ
第4章 各都道府県のケーススタディ(1)中庸型
―静岡県・香川県・兵庫県
はじめに―第4章から第7章のケーススタディについて
中庸型の三県(静岡県・香川県・兵庫県)の検討
1 静岡県―日本の社会経済システムの「縮図」における教育拡大
2 香川県―大規模化した公立高校とバッファーとしての私立高校で数年を乗り切る
3 兵庫県―大都市圏と広大な中山間地域の併存がもたらした県内の多様性
中庸型クラスターのケーススタディのまとめ
コラム 大学附属高校と高校教育拡大
第5章 各都道府県のケーススタディ(2)公立拡張型
―徳島県・愛知県
1 徳島県―山地の多い地域で「平均並み」を求める取り組みと私立高校への低い信頼感
2 愛知県―比率による高校教育機会の提供構造によって拡大した進学率
公立拡張型クラスターのケーススタディのまとめ
第6章 各都道府県のケーススタディ(3)私立拡張型
―宮崎県・山形県・群馬県
1 宮崎県―全国最低の進学率から「平均」への取り組み
2 山形県―新設された私立高校による公立高校不足の補完
3 群馬県―男女別学を前提とした高校教育機会の拡大
私立拡張型クラスターのケーススタディのまとめ
コラム 甲子園(一)
第7章 各都道府県のケーススタディ(4)大都市型
―大阪府・神奈川県
1 大阪府―マンモス私立高校による高校進学希望者の収容とその結末
2 神奈川県―急激な人口増に対応した公立高校の増設と二極化した私立高校の対応
ケーススタディによる四つのクラスターの検討のまとめ
コラム 東京(一)
コラム 東京(二)
第8章 拡大した高校教育のその後
―生徒減少期における高校教育機会の近未来像
はじめに―生徒減少期における高校教育機会提供構造の変容
1 生徒減少期における私学率の規定要因の変化
2 特徴的な県の検討?―神奈川県の事例から
3 特徴的な県の検討?―徳島県の事例から
第8章のまとめ
コラム 甲子園(二)
終 章 人口減少期における〈高卒当然社会〉のゆくえ
高校教育機会の提供構造の将来像
あとがき
初出一覧
索 引
装幀=難波園子