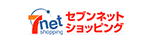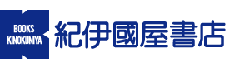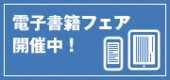乳児の対人感覚の発達
心の理論を導くもの
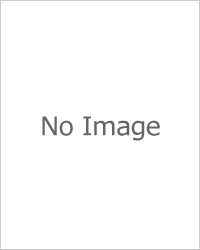
| 著者 | M. レゲァスティ 著 大藪 泰 訳 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| 出版年月日 | 2014/05/22 |
| ISBN | 9784788513907 |
| 判型・ページ数 | A5・312ページ |
| 定価 | 本体3,400円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
赤ちゃんは,いつ,どのように人の心に気づくのか? 乳児の対人理解が他者との情動共有を通して深まっていくとする立場から,多くの心理学者・哲学者が挑んできた「心の起源」「心の理論」をめぐる疑問に客観的データで迫る,乳児研究者必読の書!
乳児の対人感覚の発達――目次
はじめに
第1章 定義、理論、本書の構成
1節 心の理論の定義
2節 意図の定義
3節 心の理論の前兆としての意図
4節 理論的考察――精神状態への気づきの始まり
5節 乳児は自分を仲間と同一視する生得的能力をもって誕生する
6節 本書の構成
第2章 発達におよぼす内因的影響と外因的影響
1節 内因的要因
2節 外因的要因
3節 内因的要因、外因的要因、その相互作用
4節 乳児研究の方法
第3章 生命体/非生命体の区別
1節 社会的認知と非社会的認知との関係
2節 生命体と非生命体の区別の定義
3節 生命体と非生命体の区別に関する理論的視点
4節 人間と物を区別する乳児の能力――生後6か月間
5節 乳児は人間に意図を知覚し非生命体では知覚しない――10か月児
6節 生命体と非生命体の区別――基盤的な手がかりあるいは領域固有な表象
第4章 自己と意識
1節 哲学的省察
2節 ピアジェと自己
3節 生物―社会的理論と自己の気づき
4節 生態学的理論と自己の気づき
5節 制約的構成主義と自己の気づき
6節 物理的自己の意識
7節 社会―精神的自己の意識
8節 表象的自己の発達
9節 乳児は自分の心や身体に気づく社会的創造物である
第5章 二項的相互作用
1節 二項関係期における精神状態の気づき
2節 精神状態の起源
3節 理論的説明
4節 人間に関する領域固有な知識、制約、学習
第6章 三項的相互作用――5か月児と7か月児の共同的関わり
1節 対象物を含んだ目標の理解
2節 三項的社会スキルの発達
3節 理論の検証
4節 生後5・5から7・5か月の間で、乳児は動作と情動に意味を知覚する
第7章 乳児の対人感覚の発達に対する社会的影響
1節 社会的相互作用論者と情動調律
2節 母子相互作用の歴史的視点
3節 情動調律/情動鏡映と自己の概念
4節 情動調律、効力感と自立性の発達
第8章 情動調律と前言語的コミュニケーション
1節 母親の情動による乳児の社会認知的能力の促進
2節 前言語的コミュニケーションの発達
3節 母親の情動調律が前言語的コミュニケーションに及ぼす効果
4節 共有注意と言語発達との関係
5節 他者と心理的に関わろうとする生得的動機づけの連続性
第9章 社会的相互作用の質が乳児の原初的な欲求推理に影響する
1節 適切な対人的関係の重要性
2節 欲求推理の先行要因
3節 欲求推理に関する研究
4節 総合考察
5節 データの理論的解釈
第10章 社会的認知――情動調律、模倣、随伴性
1節 最終考察
2節 生後1・5か月と3・5か月時点でのCDM、AIMおよびAFSモデルの比較
3節 最終考察の検証
4節 社会的認知と情動共有――データの解釈
訳者あとがき
引用文献 (10)
事項索引 (3)
人名索引 (1)
装幀 臼井新太郎
カバー写真 スズキアサコ
はじめに
第1章 定義、理論、本書の構成
1節 心の理論の定義
2節 意図の定義
3節 心の理論の前兆としての意図
4節 理論的考察――精神状態への気づきの始まり
5節 乳児は自分を仲間と同一視する生得的能力をもって誕生する
6節 本書の構成
第2章 発達におよぼす内因的影響と外因的影響
1節 内因的要因
2節 外因的要因
3節 内因的要因、外因的要因、その相互作用
4節 乳児研究の方法
第3章 生命体/非生命体の区別
1節 社会的認知と非社会的認知との関係
2節 生命体と非生命体の区別の定義
3節 生命体と非生命体の区別に関する理論的視点
4節 人間と物を区別する乳児の能力――生後6か月間
5節 乳児は人間に意図を知覚し非生命体では知覚しない――10か月児
6節 生命体と非生命体の区別――基盤的な手がかりあるいは領域固有な表象
第4章 自己と意識
1節 哲学的省察
2節 ピアジェと自己
3節 生物―社会的理論と自己の気づき
4節 生態学的理論と自己の気づき
5節 制約的構成主義と自己の気づき
6節 物理的自己の意識
7節 社会―精神的自己の意識
8節 表象的自己の発達
9節 乳児は自分の心や身体に気づく社会的創造物である
第5章 二項的相互作用
1節 二項関係期における精神状態の気づき
2節 精神状態の起源
3節 理論的説明
4節 人間に関する領域固有な知識、制約、学習
第6章 三項的相互作用――5か月児と7か月児の共同的関わり
1節 対象物を含んだ目標の理解
2節 三項的社会スキルの発達
3節 理論の検証
4節 生後5・5から7・5か月の間で、乳児は動作と情動に意味を知覚する
第7章 乳児の対人感覚の発達に対する社会的影響
1節 社会的相互作用論者と情動調律
2節 母子相互作用の歴史的視点
3節 情動調律/情動鏡映と自己の概念
4節 情動調律、効力感と自立性の発達
第8章 情動調律と前言語的コミュニケーション
1節 母親の情動による乳児の社会認知的能力の促進
2節 前言語的コミュニケーションの発達
3節 母親の情動調律が前言語的コミュニケーションに及ぼす効果
4節 共有注意と言語発達との関係
5節 他者と心理的に関わろうとする生得的動機づけの連続性
第9章 社会的相互作用の質が乳児の原初的な欲求推理に影響する
1節 適切な対人的関係の重要性
2節 欲求推理の先行要因
3節 欲求推理に関する研究
4節 総合考察
5節 データの理論的解釈
第10章 社会的認知――情動調律、模倣、随伴性
1節 最終考察
2節 生後1・5か月と3・5か月時点でのCDM、AIMおよびAFSモデルの比較
3節 最終考察の検証
4節 社会的認知と情動共有――データの解釈
訳者あとがき
引用文献 (10)
事項索引 (3)
人名索引 (1)
装幀 臼井新太郎
カバー写真 スズキアサコ