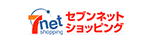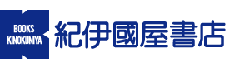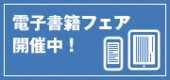災害・危機と人間
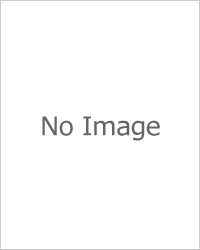
| 著者 | 日本発達心理学会 編 矢守 克也 責任編集 前川 あさ美 責任編集 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| シリーズ | 発達科学ハンドブック |
| 出版年月日 | 2013/12/17 |
| ISBN | 9784788513655 |
| 判型・ページ数 | A5・320ページ |
| 定価 | 本体3,400円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
自然災害,汚染物質,戦争,虐待といった危機的状況は,個人,家族,社会・文化にどのような影響を与えるか? 支援や防災の実例も紹介しつつ,心理学,社会学,災害文化など専門的視野から人間の行動・発達と災害・危機とのかかわりを明らかにする。
災害・危機と人間─目次
『発達科学ハンドブック』発刊にあたって
序 章 災害・危機と人間―― 矢守克也・前川あさ美
第?部 総括編
第1章 臨床・発達からみた災害・危機 前川あさ美
第1節 心の傷――トラウマ――とは
第2節 トラウマ後の心理的反応
第3節 トラウマ後の子どもの心のケア
第4節 心のケアに求められるゴール
第2章 社会・文化からみた災害・危機 矢守克也
第1節 「選択」と「運命」
第2節 「災害」と「犯罪」
第3節 「喪失」と「再生」
第4節 「世直し」と「立て直し」
第?部 領域編:人間を取りまくさまざまな災害・危機
第3章 自然災害― 近藤誠司
第1節 自然災害と時間
第2節 自然の外力にみる猶予時間の諸相
第3節 自然災害が頻発する時代における生の充溢
第4章 原子力災害(人災,福島,チェルノブイリ) 中嶋励子
第1節 福島第一原発事故と住民の避難
第2節 原子力災害が住民の心理にもたらす影響
第3節 原子力災害が地域社会にもたらした影響
第5章 戦争・テロ― 釘原直樹
第1節 集団・国家間の紛争
第2節 テロ
第6章 パンデミック― 吉川肇子
第1節 パンデミックとは
第2節 インフルエンザ・パンデミック
第3節 パンデミックの社会的影響
第7章 ネット社会が生み出す災害・危機― 関谷直也
第1節 ネット社会が危機を生成する
第2節 ネット社会が危機を拡大する
第8章 学校における災害・危機― 瀧野揚三
第1節 学校における危機と対応
第2節 学校の危機管理の概要
第3節 教職員に必要な心理教育と対応の基本
第4節 中・長期にわたる継続的支援
第9章 子どもの虐待という危機― 菅野 恵・前川あさ美
第1節 子どもの虐待が起こる背景
第2節 子どもの虐待の発見とその影響
第3節 虐待への対応・支援
第?部 キーワード編:災害・危機を解き明かす
第10章 愛着― 井上孝之
第1節 愛着とは何か
第2節 愛着形成過程における危険要因と愛着障害
第3節 東日本大震災と愛着の問題
第11章 解離性障害― 柴山雅俊
第1節 はじめに――解離の症候学
第2節 解離と病因――個体側と環境側の要因
第3節 解離と愛着
第4節 解離と外傷体験――自験例のデータから
第5節 おわりに――自己を支える場
第12章 悲嘆の心理― 金谷京子
第1節 喪失体験と悲嘆のプロセス
第2節 災害時悲嘆
第3節 サバイバーズ・ギルト
第4節 子どもの悲嘆
第5節 悲嘆のケア
第13章 レジリエンス― 川野健治
第1節 レジリエンスの軌跡
第2節 自然災害とコミュニティのレジリエンス
第3節 環境に埋め込まれた個人とレジリエンス
第14章 支援者のバーンアウト― 平野幹雄
第1節 筆者にとっての東日本大震災と喪失感
第2節 支援者のバーンアウト
第3節 支援者としての心の傷つき
第4節 支援者が自身を守るために重要なこと
第5節 まとめ
第15章 死と喪失― やまだようこ
第1節 死別と喪の作業
第2節 ナラティヴ(語り・物語)による喪失の意味づけ
第3節 語りと語り直し――ナラティヴによる死の意味の再構成
第16章 リスク認知― 上市秀雄・楠見 孝
第1節 一般市民のリスク認知の重要性
第2節 市民のリスク認知を支える情報処理過程とバイアス
第3節 専門家が留意すべきこと
第4節 まとめ
第17章 メディアの役割 外岡秀俊・今野公美子
第1節 一般向けメディアの役割と課題
第2節 子どもに災害を伝える
第18章 ボランティア(ボランティア活動,NGO)― 渥美公秀
第1節 ボランティアとは
第2節 災害ボランティア
第3節 災害ボランティアの原点への再回帰
第19章 障害者支援― 安達 潤
第1節 災害がもたらすもの
第2節 災害後の生活を支えること
第3節 発達科学にできること
第20章 防災教育― 城下英行
第1節 これまでの防災教育観
第2節 新しい地震防災教育
第3節 新たな防災教育の意味
第21章 復興のプロセス 宮本 匠
第1節 成熟社会とはなにか
第2節 成熟社会の復興プロセス
第3節 復興プロセスを記述する
第22章 コミュニティ支援 伊藤哲司
第1節 はじめに――“明るい”被災地
第2節 「心のケア」から「コミュニティ支援」へ
第3節 災害を踏まえたコミュニティ支援の事例
第4節 おわりに――支援者の立ち位置
第23章 災害・危機への研究アプローチ 八ッ塚一郎
第1節 支援と研究の「両立」
第2節 理論を通した実践
第3節 客観性の転換
第24章 学会・職能団体の連携による支援:臨床発達心理士会・
東日本大震災支援対策本部の活動を中心に 長崎 勤
第1節 学会や職能団体にとってのチャレンジとしての震災
第2節 臨床発達心理士の活動
第3節 他の学会・職能団体による支援
第4節 おわりに――「心のケア」を超えた継続的支援の方法,
そして新たな支援哲学の模索へ
第?部 事例編
第25章 乳幼児の事例
●トラウマを経験した幼児の事例 前川あさ美
第1節 乳幼児が見せるトラウマ後の反応
第2節 乳幼児の「死」の理解と喪失への反応
第3節 乳幼児が見せるポストトラウマティック プレイ
●アスペルガー症候群をもつ幼児の事例 西本絹子
第1節 対象児をめぐる問題の概要
第2節 問題状況の整理と支援
第26章 学齢期の事例
●これからの防災教育はどうあるべきか:
釜石の事例に学ぶ―― 片田敏孝
第1節 “自分の命は自分で守る”主体性を育む防災教育
●通学路の変更が登校渋りを引き起こす
要因となった事例―― 佐々木暁子
第1節 対象児をめぐる問題の概要
第2節 対象児への支援
第3節 まとめ
第27章 思春期・青年期の事例
●高校の環境防災科における防災教育 諏訪清二
第1節 防災教育の領域
第2節 学力のとらえ方
第3節 能動的な活動で育てる学力
第4節 災害ボランティア
●大学生の被災地支援― 関 嘉寛
第1節 参加の動機
第2節 対人コミュニケーション
第3節 事前・事後の学びと学生ボランティア
第28章 保護者の事例
●福島第一原発事故により避難生活を送る家族:
幼い子どもを抱える保護者の困難とは 東 敦子
第1節 事例の概要
第2節 まとめにかえて
第29章 成人期の事例
●震災遺族が「生きる希望」を見いだすとき 魚住由紀
第1節 震災後に残された遺族たち
第2節 まとめ
●阪神・淡路大震災,東日本大震災における
避難所,仮設住宅から 黒田裕子
第1節 避難所
第2節 仮設住宅
第30章 高齢者の事例
●高齢者にこそ必要な支援のあり方 中村淳子
第1節 東日本大震災における高齢者の事例
第2節 震災と高齢者の心の危機
第3節 被災した高齢者のこれから
第31章 障害児・者の事例
●自然災害と障害をめぐる国際的動向 阪本真由美
第1節 自然災害と障害のある人
第2節 阪神・淡路大震災による障害者
第3節 災害障害者支援のとりくみ――インドネシアの事例より
第4節 自然災害と障害のある人をめぐる国際的な取り組み
●東日本大震災が障害をもった子どもたちに与えた影響 須藤幸恵
第1節 避難直後の障害児
第2節 震災後2週間~4カ月の間の障害児
第3節 震災後4カ月以降の障害児
第4節 震災が障害児に与えた影響について
人名索引
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=桂川 潤
『発達科学ハンドブック』発刊にあたって
序 章 災害・危機と人間―― 矢守克也・前川あさ美
第?部 総括編
第1章 臨床・発達からみた災害・危機 前川あさ美
第1節 心の傷――トラウマ――とは
第2節 トラウマ後の心理的反応
第3節 トラウマ後の子どもの心のケア
第4節 心のケアに求められるゴール
第2章 社会・文化からみた災害・危機 矢守克也
第1節 「選択」と「運命」
第2節 「災害」と「犯罪」
第3節 「喪失」と「再生」
第4節 「世直し」と「立て直し」
第?部 領域編:人間を取りまくさまざまな災害・危機
第3章 自然災害― 近藤誠司
第1節 自然災害と時間
第2節 自然の外力にみる猶予時間の諸相
第3節 自然災害が頻発する時代における生の充溢
第4章 原子力災害(人災,福島,チェルノブイリ) 中嶋励子
第1節 福島第一原発事故と住民の避難
第2節 原子力災害が住民の心理にもたらす影響
第3節 原子力災害が地域社会にもたらした影響
第5章 戦争・テロ― 釘原直樹
第1節 集団・国家間の紛争
第2節 テロ
第6章 パンデミック― 吉川肇子
第1節 パンデミックとは
第2節 インフルエンザ・パンデミック
第3節 パンデミックの社会的影響
第7章 ネット社会が生み出す災害・危機― 関谷直也
第1節 ネット社会が危機を生成する
第2節 ネット社会が危機を拡大する
第8章 学校における災害・危機― 瀧野揚三
第1節 学校における危機と対応
第2節 学校の危機管理の概要
第3節 教職員に必要な心理教育と対応の基本
第4節 中・長期にわたる継続的支援
第9章 子どもの虐待という危機― 菅野 恵・前川あさ美
第1節 子どもの虐待が起こる背景
第2節 子どもの虐待の発見とその影響
第3節 虐待への対応・支援
第?部 キーワード編:災害・危機を解き明かす
第10章 愛着― 井上孝之
第1節 愛着とは何か
第2節 愛着形成過程における危険要因と愛着障害
第3節 東日本大震災と愛着の問題
第11章 解離性障害― 柴山雅俊
第1節 はじめに――解離の症候学
第2節 解離と病因――個体側と環境側の要因
第3節 解離と愛着
第4節 解離と外傷体験――自験例のデータから
第5節 おわりに――自己を支える場
第12章 悲嘆の心理― 金谷京子
第1節 喪失体験と悲嘆のプロセス
第2節 災害時悲嘆
第3節 サバイバーズ・ギルト
第4節 子どもの悲嘆
第5節 悲嘆のケア
第13章 レジリエンス― 川野健治
第1節 レジリエンスの軌跡
第2節 自然災害とコミュニティのレジリエンス
第3節 環境に埋め込まれた個人とレジリエンス
第14章 支援者のバーンアウト― 平野幹雄
第1節 筆者にとっての東日本大震災と喪失感
第2節 支援者のバーンアウト
第3節 支援者としての心の傷つき
第4節 支援者が自身を守るために重要なこと
第5節 まとめ
第15章 死と喪失― やまだようこ
第1節 死別と喪の作業
第2節 ナラティヴ(語り・物語)による喪失の意味づけ
第3節 語りと語り直し――ナラティヴによる死の意味の再構成
第16章 リスク認知― 上市秀雄・楠見 孝
第1節 一般市民のリスク認知の重要性
第2節 市民のリスク認知を支える情報処理過程とバイアス
第3節 専門家が留意すべきこと
第4節 まとめ
第17章 メディアの役割 外岡秀俊・今野公美子
第1節 一般向けメディアの役割と課題
第2節 子どもに災害を伝える
第18章 ボランティア(ボランティア活動,NGO)― 渥美公秀
第1節 ボランティアとは
第2節 災害ボランティア
第3節 災害ボランティアの原点への再回帰
第19章 障害者支援― 安達 潤
第1節 災害がもたらすもの
第2節 災害後の生活を支えること
第3節 発達科学にできること
第20章 防災教育― 城下英行
第1節 これまでの防災教育観
第2節 新しい地震防災教育
第3節 新たな防災教育の意味
第21章 復興のプロセス 宮本 匠
第1節 成熟社会とはなにか
第2節 成熟社会の復興プロセス
第3節 復興プロセスを記述する
第22章 コミュニティ支援 伊藤哲司
第1節 はじめに――“明るい”被災地
第2節 「心のケア」から「コミュニティ支援」へ
第3節 災害を踏まえたコミュニティ支援の事例
第4節 おわりに――支援者の立ち位置
第23章 災害・危機への研究アプローチ 八ッ塚一郎
第1節 支援と研究の「両立」
第2節 理論を通した実践
第3節 客観性の転換
第24章 学会・職能団体の連携による支援:臨床発達心理士会・
東日本大震災支援対策本部の活動を中心に 長崎 勤
第1節 学会や職能団体にとってのチャレンジとしての震災
第2節 臨床発達心理士の活動
第3節 他の学会・職能団体による支援
第4節 おわりに――「心のケア」を超えた継続的支援の方法,
そして新たな支援哲学の模索へ
第?部 事例編
第25章 乳幼児の事例
●トラウマを経験した幼児の事例 前川あさ美
第1節 乳幼児が見せるトラウマ後の反応
第2節 乳幼児の「死」の理解と喪失への反応
第3節 乳幼児が見せるポストトラウマティック プレイ
●アスペルガー症候群をもつ幼児の事例 西本絹子
第1節 対象児をめぐる問題の概要
第2節 問題状況の整理と支援
第26章 学齢期の事例
●これからの防災教育はどうあるべきか:
釜石の事例に学ぶ―― 片田敏孝
第1節 “自分の命は自分で守る”主体性を育む防災教育
●通学路の変更が登校渋りを引き起こす
要因となった事例―― 佐々木暁子
第1節 対象児をめぐる問題の概要
第2節 対象児への支援
第3節 まとめ
第27章 思春期・青年期の事例
●高校の環境防災科における防災教育 諏訪清二
第1節 防災教育の領域
第2節 学力のとらえ方
第3節 能動的な活動で育てる学力
第4節 災害ボランティア
●大学生の被災地支援― 関 嘉寛
第1節 参加の動機
第2節 対人コミュニケーション
第3節 事前・事後の学びと学生ボランティア
第28章 保護者の事例
●福島第一原発事故により避難生活を送る家族:
幼い子どもを抱える保護者の困難とは 東 敦子
第1節 事例の概要
第2節 まとめにかえて
第29章 成人期の事例
●震災遺族が「生きる希望」を見いだすとき 魚住由紀
第1節 震災後に残された遺族たち
第2節 まとめ
●阪神・淡路大震災,東日本大震災における
避難所,仮設住宅から 黒田裕子
第1節 避難所
第2節 仮設住宅
第30章 高齢者の事例
●高齢者にこそ必要な支援のあり方 中村淳子
第1節 東日本大震災における高齢者の事例
第2節 震災と高齢者の心の危機
第3節 被災した高齢者のこれから
第31章 障害児・者の事例
●自然災害と障害をめぐる国際的動向 阪本真由美
第1節 自然災害と障害のある人
第2節 阪神・淡路大震災による障害者
第3節 災害障害者支援のとりくみ――インドネシアの事例より
第4節 自然災害と障害のある人をめぐる国際的な取り組み
●東日本大震災が障害をもった子どもたちに与えた影響 須藤幸恵
第1節 避難直後の障害児
第2節 震災後2週間~4カ月の間の障害児
第3節 震災後4カ月以降の障害児
第4節 震災が障害児に与えた影響について
人名索引
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=桂川 潤