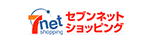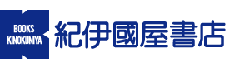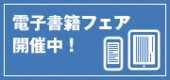発達心理学と隣接領域の理論・方法論
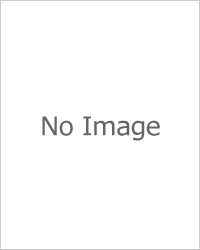
| 著者 | 日本発達心理学会 編 田島 信元 責任編集 南 徹弘 責任編集 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| シリーズ | 発達科学ハンドブック |
| 出版年月日 | 2013/03/20 |
| ISBN | 9784788513303 |
| 判型・ページ数 | A5・400ページ |
| 定価 | 本体4,000円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
「発達心理学」から,総合科学としての「発達科学」へ-発達心理学の歴史的変遷,理論的基盤と方法論の潮流をたどり,さまざまな隣接領域が発達心理学にもたらした影響を概括。発達的視点を中核においた「発達科学」としての目指すべき方向を示す。
発達心理学と隣接領域の理論・方法論――目次
『発達科学ハンドブック』発刊にあたって
序 章 発達心理学の理論・方法論の変遷と今後の展望:
発達科学を目指して 田島信元・南 徹弘
第1節 発達心理学の起源
第2節 発達心理学の展開
第3節 総合科学としての発達科学の方向性
第1章 ピアジェの認知発達理論の貢献:
過去・現在・未来 大浜幾久子
第1節 ピアジェの「臨床法」をめぐって
第2節 発生的認識論研究における心理学
第3節 ピアジェと創造性
第2章 ヴィゴツキーの文化的発達理論の貢献:
過去・現在・未来 田島信元
第1節 文化的発達理論の概要と位置づけ
第2節 文化的発達理論の展開
第3節 ヴィゴツキー理論の方法論的特徴
第3章 ボウルビィの愛着理論の貢献:
過去・現在・未来 戸田弘二
第1節 愛着の個人差を規定する要因
第2節 愛着理論の成人期への拡張
第3節 次世代の研究課題
第4章 ネオ・ピアジェ派の考え方 吉田 甫
第1節 ネオ・ピアジェ派の研究とは
第2節 ケイスの理論
第5章 新成熟論の考え方 小島康次
第1節 新成熟論とは何か
第2節 生得性とは何か――発達と進化を架橋する「制約」概念
第3節 新成熟論からみた発達――進化と文化のダイナミズム
第4節 新成熟論を支える理論
第6章 生態学的知覚論の考え方:
発達的視座から 山_寛恵・佐々木正人
第1節 理論的概説――知覚に重要な環境の事実と情報のピックアップ
第2節 発達研究における生態心理学の近年の展開
第7章 社会的学習理論の考え方 渡辺弥生
第1節 社会的学習理論の基礎理論の概説
第2節 中核となる理論と研究方法
第3節 発達心理学への影響
第8章 社会文化・歴史的発生理論の考え方 佐藤公治
第1節 道具主義的方法と文化心理学
第2節 文化的発達と媒介手段としての文化的道具
第3節 ヴィゴツキーの遊び研究と「心的体験」論
第4節 実践的行為による変革の可能性
第5節 ヴィゴツキー研究のさらなる課題
第9章 活動理論の考え方 山住勝広
第1節 活動の概念と活動システムのモデル
第2節 変化を生み出す行為の主体性への発達的介入の方法論
第3節 現代の発達心理学への活動理論の寄与
第10章 状況論の考え方:野火的活動と境界の横断 上野直樹
第1章 野火的活動と境界の横断
第2章 野火的活動の事例――オープンソース運動の略歴
第3章 オープンソース運動のもたらしたもの
第4章 野火的活動と境界の横断の再定式化
第11章 認知的社会化理論の考え方 臼井 博
第1節 認知的社会化とは――認知的社会化の2つのアプローチ
第2節 文化的剥奪仮説
第3節 心理的引き離しモデル
第4節 生物生態学モデル
第5節 まとめと今後の課題
第12章 新生児・乳児研究の考え方:
その小史と展望 川上清文・高井清子
第1節 乳児研究の歴史
第2節 乳児研究の方法
第3節 最近の乳児研究の例
第13章 生涯発達心理学の考え方:発達の可塑性 鈴木 忠
第1節 生涯発達心理学の成立
第2節 サクセスフルエイジングと可塑性
第3節 発達の自己制御
第14章 比較行動学の考え方 南 徹弘
第1節 行動比較研究の背景
第2節 比較行動学における「行動」
第3節 比較行動学の課題
第4節 「サル類―チンパンジー―ヒト」の身体成長の比較発達
第15章 霊長類学の考え方 中村徳子
第1節 霊長類学とは
第2節 比較発達心理学とは
第3節 霊長類学からみる発達的アプローチ――こころの進化的起源
第16章 行動遺伝学の考え方 児玉典子
第1節 行動遺伝学とは
第2節 発達心理学への行動遺伝学の貢献
第17章 進化学(進化心理学)の考え方 富原一哉
第1節 理論的特徴
第2節 方法論的特徴
第3節 現代発達心理学への寄与のあり方
第18章 文化人類学の考え方:文化と発達 高田 明
第1節 文化人類学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第4節 まとめに代えて
第19章 ダイナミック・システムズ・アプローチの
考え方 陳 省仁
第1節 DSAの基本的考え方
第2節 DSTの主な用語と概念
第3節 DSAの研究方略
第4節 DSAと他の主な発達理論との比較
第5節 結び
第20章 社会言語学の考え方 岡本能里子
第1節 社会言語学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第4節 研究領域の広がりと今後の展望
第21章 認知科学の考え方 島田英昭・海保博之
第1節 認知科学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第22章 教育学の考え方:発達の観念と教育研究 古賀正義
第1節 教育学研究の歴史と発達の科学
第2節 教育学研究の方法的変化と発達への接近
第3節 発達研究への教育学の貢献
第23章 家族社会学の考え方 大和礼子
第1節 1つめの変化――「発達は時代・社会によって多様」
第2節 2つめの変化――「多様な人間関係の中での育児」
第24章 エスノメソドロジー(社会学)の考え方 高木智世
第1節 エスノメソドロジーの視点
第2節 会話分析を通して見えるもの
第3節 発達心理学への提言
第25章 エスノグラフィの考え方 柴山真琴
第1節 エスノグラフィの概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢
第26章 現象学の考え方:
「他者と時間」の現象学を中心にして 増山真緒子
第1節 はじめに――「老いること」「死にゆくこと」
第2節 老いの現象学
第3節 レヴィナスと現象学
第4節 ハイデッガーと「死に臨むこと」
第5章 生きること,死ぬこと
第27章 小児科学の考え方 小西行郎
第1節 神経科学から
第2節 胎児の行動観察から
第28章 精神医学の考え方 本城秀次
第1節 了解概念と発達概念
第2節 精神分析における発達概念
第3節 診断としての発達障害
第4節 神経発達仮説
第29章 脳科学の考え方 皆川泰代
第1節 脳科学の概念
第2節 方法論の特徴と発達心理学への貢献
第3節 機能一般的な処理から機能特異的処理へ
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=桂川 潤
『発達科学ハンドブック』発刊にあたって
序 章 発達心理学の理論・方法論の変遷と今後の展望:
発達科学を目指して 田島信元・南 徹弘
第1節 発達心理学の起源
第2節 発達心理学の展開
第3節 総合科学としての発達科学の方向性
第1章 ピアジェの認知発達理論の貢献:
過去・現在・未来 大浜幾久子
第1節 ピアジェの「臨床法」をめぐって
第2節 発生的認識論研究における心理学
第3節 ピアジェと創造性
第2章 ヴィゴツキーの文化的発達理論の貢献:
過去・現在・未来 田島信元
第1節 文化的発達理論の概要と位置づけ
第2節 文化的発達理論の展開
第3節 ヴィゴツキー理論の方法論的特徴
第3章 ボウルビィの愛着理論の貢献:
過去・現在・未来 戸田弘二
第1節 愛着の個人差を規定する要因
第2節 愛着理論の成人期への拡張
第3節 次世代の研究課題
第4章 ネオ・ピアジェ派の考え方 吉田 甫
第1節 ネオ・ピアジェ派の研究とは
第2節 ケイスの理論
第5章 新成熟論の考え方 小島康次
第1節 新成熟論とは何か
第2節 生得性とは何か――発達と進化を架橋する「制約」概念
第3節 新成熟論からみた発達――進化と文化のダイナミズム
第4節 新成熟論を支える理論
第6章 生態学的知覚論の考え方:
発達的視座から 山_寛恵・佐々木正人
第1節 理論的概説――知覚に重要な環境の事実と情報のピックアップ
第2節 発達研究における生態心理学の近年の展開
第7章 社会的学習理論の考え方 渡辺弥生
第1節 社会的学習理論の基礎理論の概説
第2節 中核となる理論と研究方法
第3節 発達心理学への影響
第8章 社会文化・歴史的発生理論の考え方 佐藤公治
第1節 道具主義的方法と文化心理学
第2節 文化的発達と媒介手段としての文化的道具
第3節 ヴィゴツキーの遊び研究と「心的体験」論
第4節 実践的行為による変革の可能性
第5節 ヴィゴツキー研究のさらなる課題
第9章 活動理論の考え方 山住勝広
第1節 活動の概念と活動システムのモデル
第2節 変化を生み出す行為の主体性への発達的介入の方法論
第3節 現代の発達心理学への活動理論の寄与
第10章 状況論の考え方:野火的活動と境界の横断 上野直樹
第1章 野火的活動と境界の横断
第2章 野火的活動の事例――オープンソース運動の略歴
第3章 オープンソース運動のもたらしたもの
第4章 野火的活動と境界の横断の再定式化
第11章 認知的社会化理論の考え方 臼井 博
第1節 認知的社会化とは――認知的社会化の2つのアプローチ
第2節 文化的剥奪仮説
第3節 心理的引き離しモデル
第4節 生物生態学モデル
第5節 まとめと今後の課題
第12章 新生児・乳児研究の考え方:
その小史と展望 川上清文・高井清子
第1節 乳児研究の歴史
第2節 乳児研究の方法
第3節 最近の乳児研究の例
第13章 生涯発達心理学の考え方:発達の可塑性 鈴木 忠
第1節 生涯発達心理学の成立
第2節 サクセスフルエイジングと可塑性
第3節 発達の自己制御
第14章 比較行動学の考え方 南 徹弘
第1節 行動比較研究の背景
第2節 比較行動学における「行動」
第3節 比較行動学の課題
第4節 「サル類―チンパンジー―ヒト」の身体成長の比較発達
第15章 霊長類学の考え方 中村徳子
第1節 霊長類学とは
第2節 比較発達心理学とは
第3節 霊長類学からみる発達的アプローチ――こころの進化的起源
第16章 行動遺伝学の考え方 児玉典子
第1節 行動遺伝学とは
第2節 発達心理学への行動遺伝学の貢献
第17章 進化学(進化心理学)の考え方 富原一哉
第1節 理論的特徴
第2節 方法論的特徴
第3節 現代発達心理学への寄与のあり方
第18章 文化人類学の考え方:文化と発達 高田 明
第1節 文化人類学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第4節 まとめに代えて
第19章 ダイナミック・システムズ・アプローチの
考え方 陳 省仁
第1節 DSAの基本的考え方
第2節 DSTの主な用語と概念
第3節 DSAの研究方略
第4節 DSAと他の主な発達理論との比較
第5節 結び
第20章 社会言語学の考え方 岡本能里子
第1節 社会言語学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第4節 研究領域の広がりと今後の展望
第21章 認知科学の考え方 島田英昭・海保博之
第1節 認知科学の概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢献
第22章 教育学の考え方:発達の観念と教育研究 古賀正義
第1節 教育学研究の歴史と発達の科学
第2節 教育学研究の方法的変化と発達への接近
第3節 発達研究への教育学の貢献
第23章 家族社会学の考え方 大和礼子
第1節 1つめの変化――「発達は時代・社会によって多様」
第2節 2つめの変化――「多様な人間関係の中での育児」
第24章 エスノメソドロジー(社会学)の考え方 高木智世
第1節 エスノメソドロジーの視点
第2節 会話分析を通して見えるもの
第3節 発達心理学への提言
第25章 エスノグラフィの考え方 柴山真琴
第1節 エスノグラフィの概念
第2節 方法論の特徴
第3節 発達心理学への貢
第26章 現象学の考え方:
「他者と時間」の現象学を中心にして 増山真緒子
第1節 はじめに――「老いること」「死にゆくこと」
第2節 老いの現象学
第3節 レヴィナスと現象学
第4節 ハイデッガーと「死に臨むこと」
第5章 生きること,死ぬこと
第27章 小児科学の考え方 小西行郎
第1節 神経科学から
第2節 胎児の行動観察から
第28章 精神医学の考え方 本城秀次
第1節 了解概念と発達概念
第2節 精神分析における発達概念
第3節 診断としての発達障害
第4節 神経発達仮説
第29章 脳科学の考え方 皆川泰代
第1節 脳科学の概念
第2節 方法論の特徴と発達心理学への貢献
第3節 機能一般的な処理から機能特異的処理へ
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=桂川 潤