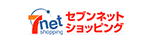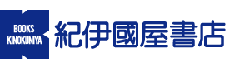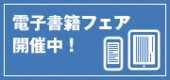安全と危険のメカニズム
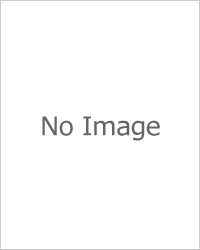
| 著者 | 重野 純 著 福岡 伸一 著 柳原 敏夫 著 |
|---|---|
| ジャンル | 科学・科学論 |
| 出版年月日 | 2011/03/20 |
| ISBN | 9784788512283 |
| 判型・ページ数 | A5・232ページ |
| 定価 | 本体2,400円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
科学技術が便利さを生みだす一方で生活を脅かすという状況が生まれている。食品添加物や遺伝子組み換え等による健康への危険,医療事故など,人間が生みだす危険にどう対処していったらよいのか。心理学,分子生物学,法律の3立場からの検証と討論。
安全と危険のメカニズム――目次
まえがき
第1章 家庭生活における安全と危険 重野 純
はじめに
1 食べる
1-1 五感
1-2 食べることの意義
1-3 毎日の食事における味覚の信頼性
1-4 食べ物の色と形が味覚判断に与える影響
1-5 視覚を味覚に取り入れた料理の達人─北大路魯山人
1-6 食生活の中に潜む危険
2 風呂に入る
2-1 風呂の歴史
2-2 日本人は風呂好き
2-3 入浴剤の効用と危険
3 インターホンに出る
4 あなたには分かりますか─その音は安全?危険?
5 安全と危険を分けるもの
第2章 食の安全と危険 福岡伸一
1 食の安全と危険
1-1 毒と薬は表裏一体
1-2 食の安心・安全をめざす評価系確立の意義
2 消化管における「細菌受容体」の発見
2-1 GP2ノックアウトマウスを用いた経口感染リスクの評価系
2-2 この発見は何に役立つのか─経口ワクチンの可能性
2-3 残された謎
3 GP2ノックアウトマウスを用いた経口リスク評価系研究の新展開
3-1 付着因子 FimH 陽性細菌がM細胞に発現するGP2を介して
取り込まれることで、粘膜免疫応答が開始される
3-2 パイエル板におけるGP2依存性抗原取り込み機構
3-3 まとめ
4 QPRTノックアウトマウスを用いた必須アミノ酸摂取上限の研究
─その1 分子生物学的アプローチ
4-1 はじめに
4-2 実験材料と方法
4-3 マウス生体内におけるQPRT発現の確認
4-4 トリプトファン過剰摂取による影響の解析
4-5 結果
4-6 考察
5 QPRTノックアウトマウスを用いた必須アミノ酸摂取上限の研究
─その2 行動学的アプローチ
5-1 QPRTノックアウトマウスの飼育
5-2 遺伝子発現解析に用いたマウス
5-3 リアルタイムPCR法による遺伝子発現解析
5-4 QPRTノックアウトマウスの行動的特性
6 トリプトファン代謝経路酵素の遺伝子発現解析による
キノリン酸蓄積メカニズムの解明
6-1 リアルタイムPCR法による遺伝子発現解析
6-2 QPRTノックアウトマウスの行動的特性
第3章 市民の科学への不信はいかにして形成されるか
─「歪曲」されたリスク評価の事例の検討 柳原敏夫
はじめに─問題の分類
1 古典的リスク評価の検討─事例検討
1-1 遺伝子組換え技術
1-2 遺伝子組換え技術は二度操作する
1-3 遺伝子組換え技術の事例─GMイネの野外実験
1-4 悪夢から眺めた仮説
1-5 古典的テーマ─耐性菌問題
1-6 仮説の検証(一度目の操作:研究段階)
1-7 仮説の検証(二度目の操作その1:国の事前審査の段階)
─消えた耐性菌問題
1-8 仮説の検証(二度目の操作その2:裁判手続の段階)
─耐性菌問題の創作物語
1-9 世論操作の動機(最大の評価ミス:ディフェンシン耐性菌の危険性について)
1-10 二度目の操作の防止
2 現代型リスク評価の検討─理論検討
2-1 問題の提起
2-2 リスク評価の基本問題
2-3 リスク評価とは何か(その1)
2-4 リスク評価とは何か(その2)
2-5 リスク評価とは何か(その3)
2-6 リスク評価とは何か(その4)
2-7 リスク評価とは何か(その5)
2-8 リスク評価の迷妄の打破のために
2-9 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその1)
2-10 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその2)
2-11 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその3)
2-12 リスク評価論の外(科学裁判の躓き)
2-13 リスク評価論の躓き
2-14 科学の限界の不承認について
2-15 善(倫理・法律)の判断とはどういうことか
2-16 美(快・不快)の判断とはどういうことか
2-17 リスク評価の判断者とは誰か
2-18 現代型リスク評価の課題(小括)
2-19 法律家にとってのリスク評価(食の安全と職の安全)
2-20 法律家にとってのリスク評価(法律家の戸惑いの告白)
座談会
本書の誕生まで
第1章「家庭生活における安全と危険」について
第2章「食の安全と危険」について
第3章「市民の科学への不信はいかにして形成されるか」について
アシロマ会議
生物の動的平衡の考えは、なぜ異端なのか
「不確実な事態」の背景
リスクとデインジャー
現象を評価する三つのレベル
科学とリスク評価
リスクと人間の文脈
科学技術と人間
おわりに─人災と自然災害の峻別
注
装丁=虎尾 隆
まえがき
第1章 家庭生活における安全と危険 重野 純
はじめに
1 食べる
1-1 五感
1-2 食べることの意義
1-3 毎日の食事における味覚の信頼性
1-4 食べ物の色と形が味覚判断に与える影響
1-5 視覚を味覚に取り入れた料理の達人─北大路魯山人
1-6 食生活の中に潜む危険
2 風呂に入る
2-1 風呂の歴史
2-2 日本人は風呂好き
2-3 入浴剤の効用と危険
3 インターホンに出る
4 あなたには分かりますか─その音は安全?危険?
5 安全と危険を分けるもの
第2章 食の安全と危険 福岡伸一
1 食の安全と危険
1-1 毒と薬は表裏一体
1-2 食の安心・安全をめざす評価系確立の意義
2 消化管における「細菌受容体」の発見
2-1 GP2ノックアウトマウスを用いた経口感染リスクの評価系
2-2 この発見は何に役立つのか─経口ワクチンの可能性
2-3 残された謎
3 GP2ノックアウトマウスを用いた経口リスク評価系研究の新展開
3-1 付着因子 FimH 陽性細菌がM細胞に発現するGP2を介して
取り込まれることで、粘膜免疫応答が開始される
3-2 パイエル板におけるGP2依存性抗原取り込み機構
3-3 まとめ
4 QPRTノックアウトマウスを用いた必須アミノ酸摂取上限の研究
─その1 分子生物学的アプローチ
4-1 はじめに
4-2 実験材料と方法
4-3 マウス生体内におけるQPRT発現の確認
4-4 トリプトファン過剰摂取による影響の解析
4-5 結果
4-6 考察
5 QPRTノックアウトマウスを用いた必須アミノ酸摂取上限の研究
─その2 行動学的アプローチ
5-1 QPRTノックアウトマウスの飼育
5-2 遺伝子発現解析に用いたマウス
5-3 リアルタイムPCR法による遺伝子発現解析
5-4 QPRTノックアウトマウスの行動的特性
6 トリプトファン代謝経路酵素の遺伝子発現解析による
キノリン酸蓄積メカニズムの解明
6-1 リアルタイムPCR法による遺伝子発現解析
6-2 QPRTノックアウトマウスの行動的特性
第3章 市民の科学への不信はいかにして形成されるか
─「歪曲」されたリスク評価の事例の検討 柳原敏夫
はじめに─問題の分類
1 古典的リスク評価の検討─事例検討
1-1 遺伝子組換え技術
1-2 遺伝子組換え技術は二度操作する
1-3 遺伝子組換え技術の事例─GMイネの野外実験
1-4 悪夢から眺めた仮説
1-5 古典的テーマ─耐性菌問題
1-6 仮説の検証(一度目の操作:研究段階)
1-7 仮説の検証(二度目の操作その1:国の事前審査の段階)
─消えた耐性菌問題
1-8 仮説の検証(二度目の操作その2:裁判手続の段階)
─耐性菌問題の創作物語
1-9 世論操作の動機(最大の評価ミス:ディフェンシン耐性菌の危険性について)
1-10 二度目の操作の防止
2 現代型リスク評価の検討─理論検討
2-1 問題の提起
2-2 リスク評価の基本問題
2-3 リスク評価とは何か(その1)
2-4 リスク評価とは何か(その2)
2-5 リスク評価とは何か(その3)
2-6 リスク評価とは何か(その4)
2-7 リスク評価とは何か(その5)
2-8 リスク評価の迷妄の打破のために
2-9 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその1)
2-10 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその2)
2-11 リスク評価論の外(芸術裁判の躓きその3)
2-12 リスク評価論の外(科学裁判の躓き)
2-13 リスク評価論の躓き
2-14 科学の限界の不承認について
2-15 善(倫理・法律)の判断とはどういうことか
2-16 美(快・不快)の判断とはどういうことか
2-17 リスク評価の判断者とは誰か
2-18 現代型リスク評価の課題(小括)
2-19 法律家にとってのリスク評価(食の安全と職の安全)
2-20 法律家にとってのリスク評価(法律家の戸惑いの告白)
座談会
本書の誕生まで
第1章「家庭生活における安全と危険」について
第2章「食の安全と危険」について
第3章「市民の科学への不信はいかにして形成されるか」について
アシロマ会議
生物の動的平衡の考えは、なぜ異端なのか
「不確実な事態」の背景
リスクとデインジャー
現象を評価する三つのレベル
科学とリスク評価
リスクと人間の文脈
科学技術と人間
おわりに─人災と自然災害の峻別
注
装丁=虎尾 隆