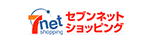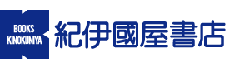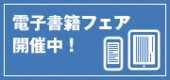音楽はいかに現代社会をデザインしたか
教育と音楽の大衆社会史
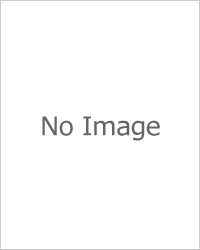
| 著者 | 上田 誠二 著 |
|---|---|
| ジャンル | 社会学 > 歴史社会学 |
| 出版年月日 | 2010/06/30 |
| ISBN | 9784788512009 |
| 判型・ページ数 | A5・408ページ |
| 定価 | 本体4,200円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
内容説明
目次
退廃的で堕落しているといわれた中山晋平の「東京音頭」は,なぜ戦中に「建国音頭」,戦後は「憲法音頭」に変容したのか。北原白秋の「国民歌謡」,総力戦下の絶対音感教育などとの対比で,音楽と聴覚の社会形成力を鮮やかに抉出した気鋭の力作評論。
◆音楽はいかに現代社会をデザインしたか――目次
まえがき
各章の流れ
序 章 文化史の方法
第一節 子守唄と合唱の現代
第二節 教育と音楽の大衆社会史
第三節 教育という社会デザインと音楽という技法の親和性
第四節 文化としての教育
第五節 一九二〇―五〇年代の文化と社会
第六節 大正期までの文芸と音楽の教育
第七節 大磯町という地域
第一部 大衆社会の形成と芸術教育の誕生 一九二〇―三〇年代
第一章 北原白秋による芸術教育と公民育成
子どものための童謡から大人のための民謡へ
第一節 児童文学からの出発と展開
第二節 現代的な職業のための労作唄
第三節 芸術的歌謡と大衆的歌謡の対抗と調整
本章のまとめ
第二章 エリート音楽教師たちの音楽教育運動
日本教育音楽協会の設立と展開
第一節 日本教育音楽協会の設立
第二節 音楽教育の社会的効用をめぐって
第三節 全国音楽教育研究大会の開催
本章のまとめ
第三章 地域社会における都市化と芸術教育の展開
神奈川県中郡大磯町を事例として
第一節 文集『磯の光』創刊の背景
第二節 『磯の光』の提示する子どもらしさ
第三節 都市化の波及と子どもらしさの具体化・社会化
本章のまとめ
第二部 芸術文化・学校文化・大衆文化の境界線 一九三〇―四〇年代
第四章 北原白秋・山田耕筰による国民歌謡の芸術世界
芸術文化の大衆化と大衆の国民化
第一節 北原白秋の国民歌謡の特徴
第二節 二つの郷土愛の融合
第三節 国民歌謡のコスモロジー
本章のまとめ
第五章 日本教育音楽協会による社会の芸術化運動
学校文化の芸術化と国民学校芸能科音楽の創設
第一節 文部官僚乗杉嘉壽の会長就任
第二節 社会の芸術化運動
第三節 国民学校芸能科音楽の創設
本章のまとめ
第六章 「東京音頭」から「建国音頭」へ
大衆文化の教育化
第一節 流行歌の社会的使命
第二節 敵視される晋平節
第三節 「東京音頭」から「建国音頭」へ
本章のまとめ
第三部 教育と音楽による現代的秩序意識の形成 一九四〇―五〇年代
第七章 「文化としての教育」の自律性
戦中・戦後の神奈川県中郡大磯町を事例として
第一節 総力戦下の芸術教育
第二節 戦後青年文化運動の出発
第三節 青年会の政治運動・文芸運動
第四節 政治運動・文芸運動の行方
本章のまとめ
第八章 総力戦下の絶対音感という自立美 芸術と国防のための能力主義、その顛末
第一節 音感教育の導入過程
第二節 国民学校における音感教育の実践と展開神奈川県中郡大磯町を中心に
第三節 盲教育界における音感教育の実践と防空監視への動員
本章のまとめ
第九章 戦後民主主義下の相対音感という調和美 文化国家の社会秩序、その起源と行方
第一節 戦後における音楽教師集団の芸術教育運動
第二節 戦後における公定の芸術教育
第三節 排除された大衆文化の可能性
本章のまとめ
終 章 将来への若干の展望
第一節 地域社会の自律性を目指して
第二節 「文化としての教育」を目指して
注
あとがき
初出一覧
図版出典一覧
関連年表
索引
装幀 難波園子
まえがき
各章の流れ
序 章 文化史の方法
第一節 子守唄と合唱の現代
第二節 教育と音楽の大衆社会史
第三節 教育という社会デザインと音楽という技法の親和性
第四節 文化としての教育
第五節 一九二〇―五〇年代の文化と社会
第六節 大正期までの文芸と音楽の教育
第七節 大磯町という地域
第一部 大衆社会の形成と芸術教育の誕生 一九二〇―三〇年代
第一章 北原白秋による芸術教育と公民育成
子どものための童謡から大人のための民謡へ
第一節 児童文学からの出発と展開
第二節 現代的な職業のための労作唄
第三節 芸術的歌謡と大衆的歌謡の対抗と調整
本章のまとめ
第二章 エリート音楽教師たちの音楽教育運動
日本教育音楽協会の設立と展開
第一節 日本教育音楽協会の設立
第二節 音楽教育の社会的効用をめぐって
第三節 全国音楽教育研究大会の開催
本章のまとめ
第三章 地域社会における都市化と芸術教育の展開
神奈川県中郡大磯町を事例として
第一節 文集『磯の光』創刊の背景
第二節 『磯の光』の提示する子どもらしさ
第三節 都市化の波及と子どもらしさの具体化・社会化
本章のまとめ
第二部 芸術文化・学校文化・大衆文化の境界線 一九三〇―四〇年代
第四章 北原白秋・山田耕筰による国民歌謡の芸術世界
芸術文化の大衆化と大衆の国民化
第一節 北原白秋の国民歌謡の特徴
第二節 二つの郷土愛の融合
第三節 国民歌謡のコスモロジー
本章のまとめ
第五章 日本教育音楽協会による社会の芸術化運動
学校文化の芸術化と国民学校芸能科音楽の創設
第一節 文部官僚乗杉嘉壽の会長就任
第二節 社会の芸術化運動
第三節 国民学校芸能科音楽の創設
本章のまとめ
第六章 「東京音頭」から「建国音頭」へ
大衆文化の教育化
第一節 流行歌の社会的使命
第二節 敵視される晋平節
第三節 「東京音頭」から「建国音頭」へ
本章のまとめ
第三部 教育と音楽による現代的秩序意識の形成 一九四〇―五〇年代
第七章 「文化としての教育」の自律性
戦中・戦後の神奈川県中郡大磯町を事例として
第一節 総力戦下の芸術教育
第二節 戦後青年文化運動の出発
第三節 青年会の政治運動・文芸運動
第四節 政治運動・文芸運動の行方
本章のまとめ
第八章 総力戦下の絶対音感という自立美 芸術と国防のための能力主義、その顛末
第一節 音感教育の導入過程
第二節 国民学校における音感教育の実践と展開神奈川県中郡大磯町を中心に
第三節 盲教育界における音感教育の実践と防空監視への動員
本章のまとめ
第九章 戦後民主主義下の相対音感という調和美 文化国家の社会秩序、その起源と行方
第一節 戦後における音楽教師集団の芸術教育運動
第二節 戦後における公定の芸術教育
第三節 排除された大衆文化の可能性
本章のまとめ
終 章 将来への若干の展望
第一節 地域社会の自律性を目指して
第二節 「文化としての教育」を目指して
注
あとがき
初出一覧
図版出典一覧
関連年表
索引
装幀 難波園子